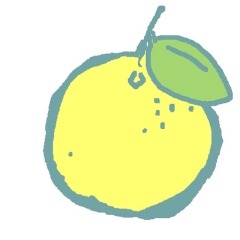[Springreport]
■アンチノミー
笑えない、といった彼に向けて自分が言ったのは、それでも「笑うことはできる」という事だった。
この業界で生きている上で、いいえ、生きていく上で笑いたくなくても笑わないといけないときがある。感情をそのままに生きていくことなど、あまりにも難しい。
HAYATOであったころに。痛く感じたことだ。心で一ミリたりとも笑わなくとも、口角をあげれば笑える。ウィスキーと唱えれば、口角はその形になる。それを繰り返せば、きっと慣れる。思えば、自分にも余裕がなかったのもあった。嘘をつくことが必要なときもある。そう伝えたかったのには、言葉がたりなさすぎて、それでいて口にする言葉はすべて己に突き刺さるものだった。
「そう、だよね」
彼は、口の端に二本の指を添え、押し上げた。笑う方法を知っていた。それが、あまりにも歪に滑稽で悲しく、愛おしいと思った。
『大丈夫だよ』
大丈夫じゃないときに出る、大丈夫。
渋谷さんはそんなことを言う音也にきっぱりと「うざい」といえたそうだ。彼女の強さを羨ましいと思う時がある。そうだ。見るからに大丈夫じゃない人間の大丈夫など、気にしてくれと言っているようなものだ。そこまでは解る。その先の扉を開いていいものかどうか。それを聞いて、その先を担うことができるのか。それが恐ろしいのだ。引き出しを開いたとして、その責任を取ることができるかの覚悟が、取れるかどうかが怖いのだ。
事あるごとに「大丈夫」という言葉に何度も苛立った。根拠のない言葉なら言わないでほしいと。
それが、生きるための呪文だったと理解したのは、程なくして。
悲しみとは何からわき出でるものか。喜びと悲しみの源泉はいつの時もひとつ。心がどう汲み取るか。どうしてそうもアンチノミーなモノを生み出せるのか。それは人間だからだ。人間が思考を持つ生き物だから。それを失えば、今の己の目指すものすら生まれなかったかもしれない。
音也が抱えていた悲嘆を目にして、そう思われる。
失ったものを埋めるように。失った母親がでてこないよう。その空いた穴を必死に埋めていた。
「太陽のようであれ」
その言葉だけが彼の車輪だった。
日常見上げる空にある存在として、目にするそれが、言葉を忘れず思いださせてくれたのだろう。
繰り返していた言葉。
『生きてるならなんとかなるかもしれない』
相手が生きているからこそ苦しいこともある。希望が捨てきれず歩み寄れず、元の形に収まらないもどかしさを、伝え解くことはできない。それでも、ええ、あのドラマを見た時に其れだとわかりました。伝えたい相手に言葉を聞いてもらえないとは、どういうことかと。
音也がつかみ取った役は寿さんの弟役。ミュージシャンを目指し家を出た兄と、残る家族を支える弟。そんな殊勝な役柄ができるのだろうか。
「施設ではチビの兄ちゃんしてたし、お兄さんもお姉さんも沢山いた」
と、台本を目に固まる姿。
家族という形のあり方に不安を抱く音也に、語った自分も、本当にそれを理解しいているとは思えなかった。
実際に観た映画は杞憂を通り越し、今までの知りえなかった時間を垣間見るようでもあった。ああ。無鉄砲に無邪気に無遠慮にふるまう彼だけが彼をなしえるものではないと。
病院でのシーンが、話題となったシーン。
見る人は演技力を褒め称えた。
知るものが見れば、それはパンドラの箱が開かれた瞬間だった。とても危うく、リアルがあった。それこそ彼の中の追憶、箱から飛び出したのは悲しみ、怒り、後悔。それに気づけなかった自分の未熟さも。それを受け止めることを許された兄役の男に覚えた怒りも。
ああ、あれは嫉妬だ。兄の腕の中で震えながら泣く姿に、それを本当の兄のように抱き締める寿さんへの言い知れない嫉妬を感じたのだ。
「いたっ」
「どうしたんですか?」
「台本で手切っちゃった。でもこれくらいなら大丈夫だよ」
ちろりと覗く舌先の赤が、小さく膨れ上がる赤い血を舐めとる。
口癖のようにいう言葉は、日常の中にあふれる。
理解したとてその言葉が聞きたいわけではない。
大丈夫じゃないなら、大丈夫じゃないといってほしい。
それを理解できる人間に、私はなりたい。人は一朝一夕には変われないことは自分でもよく知っている。でも理解しあいたい。明日へと結んでいくためにも。
そう願うばかりです。ダメですね。私も、結局まだ願うだけで、それを持つ覚悟ができない臆病さを捨てきれない。
「行儀が悪いですよ。ほら、手を貸してください」
「ありがとう、って、トキヤ!?」
強く握れば新たに膨れ上がる赤を、同じように舐めとる。どうせ止血を施されるのであろうと思っていたのだろう。しますよ、ちゃんと。自分でしたときはおざなりの癖に、人がすると途端あわてふためく。まあ、無理もない。他人にそんなことされて快いわけない。どうしてこのシチュエーションはテンプレートとしてあるのか。そう思いながら、彼が生きている証拠でありながら、到底美味とはいえぬ感覚が口に拡がる。
「だいじょうぶ?不味くない?」
「大丈夫です。ちゃんと不味いですよ。血の味が美味しいと感じたら、ドラキュラなのかもしれませんね。ほら、手を洗いに行きますよ」
「不味いんじゃん。どうしたのさ、今日は」
「シチュエーションに対しての見解を広めようと思いまして。いざやると、これが絵になるのか疑問が浮かびましたが」
「いや、こっちとしては、かなり心臓に悪い……」
居心地悪そうに目をそらすが、かまうものか。
彼からよく綺麗好きだの潔癖だの、言われている。確かに、他人の血など舐めても不衛生極まりないのに。あなたはそもそも、私がそれを許す相手になっていることに気付かないのか。私がこうする意味を、もっと深く考えてください。
・