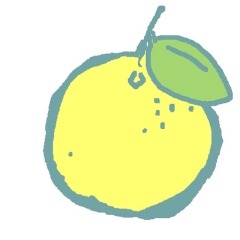鬼龍がレッスン室の扉を開くと第一声に。
「で、隊長は今回なにやらかしたんですか?」
「また何をやらかしたでござるか」
「あらら〜」
「俺にもさっぱりわからん!」
「……お前が原因って所は否定しないのかよ」
「あ。大将!」
流星隊一同はレッスン室のど真ん中で頭を付き合わせていた。
「大まかなことは皆に説明したっす!」
鬼龍の来訪により件の二人が揃ったのだ。状況を初めて目にする仙石と高峯、深海は事の真相を見守る。まず誰彼に元気の良い挨拶を第一声目に行うところだが、それがない。何時もと違うことだけは伺えるが、見慣れた光景を光景を目にしている面々にはにわかには信じがたいものだ。
南雲の視線の先を必死で追うようにして守沢が鬼龍の位置を辿ろうとする。
「あの、隊長…本当に全く鬼龍先輩のことが見えていないんですか?」
「拙者から見たら何時もの光景に変わりないようにみえるが…」
高峯と仙石が一緒に頭をひねった。
「そうっすよねぇ…正直未だに変な感じっすよ」
「う、うむ……。俺には鬼龍がどこにいるか、全然…まったく分からないんだ。お前たちがいたら何となく視線の持っていき方で方向は分かりはするのだが、正確な位置は分からないし、なんと言っているのかも、分からないんだ…」
言葉にしながら困惑してきた。わからない状況が多すぎて、どこから手をつけて考え始めればいいのかすらわからなくなる。
「『あかおに』さんはちあきのことはっきり『みえる』んですよね?」
「おう。ほらよ」
「うわっ!」
肩に手を置いただけで幽霊にでも触れられたような叫び声だ。ようやく南雲から受けた説明が現実のものだと飲み込めた。
「ずっと一緒なら手を繋いでおけばいいと思うけど…」
「それは羨ましいっす!俺も大将と手を……?う〜みゅ、それは何だかいけない気が…」
「手間はかからねぇが、俺達が手を繋いで歩き回ってちゃぁ変な目で見られるだろう。守沢以外には普通に見えてるんだからよ」
「っすよね」
後輩は三者三様に仲良くお手手つなぎながら学園を往来する二人の姿を思い浮かべる。決して微笑ましく眺められる光景ではない。しかもただでさえ学園内で名の知れ渡っている二人だから目立つ事この上ないだろう。
「『ばつ』げーむのたすきをかけておきますか?すこしくらい『かもふらーじゅ』できますよ」
「なるほどな。タスキ作りなら任せろ」
「そこ頑張らなくていいっすから!もう!」
脱線しつつある会話に脱力する。確かに一日中程度ならそれでなんとか誤魔化せるかもしれないが、当面終息の手が見つからないのである。明日ぽっと治ればそれに越したことはないのだが。
さて。目の前で交わされるやり取りに頃合を図りかねている守沢の様子に南雲が気付いた。鬼龍は何か言ったのか?と聞きたくてうずうずしている様に一つ咳払いし、そうでしたね、と鬼龍の言葉を復唱する。別に声音を真似しなくてもいいのだが、南雲なりに鬼龍の言葉をできる限りそのまま伝えようとしている。
「手旗信号みたいなものがあれば…いいと思うんだけど。イエスかノーくらい伝われば…」
「手旗……信号……合図…………あ!それなら!」
高峯のその言葉にはっと何かひらめいた仙石が鞄を漁る。取り出したのはカエルの人形と小さな鈴のついたストラップだ。
「これは如何でござろうか」
「わぁそのカエル可愛い」
「転校生殿からいただいたでござる。鬼龍殿にこれを持っていてもらうのはどうだろう?忍とは例え闇の中でも音さえあれば動きを感知するもの。隊長殿も音を頼りにすれば幾分か鬼龍殿の姿も認識できるやもしないでござる」
鈴を二回振ってみた。
チリンチリンと軽やかな音に守沢の身体がピクリと反応する。
「お!聞こえるぞ!」
その声にまたチリンと鈴を鳴らす。
「おお!凄いな仙石妙案だ!鬼龍!」
相槌を打つように鈴が鳴る。守沢が嬉しそうに顔を赤らめた。会話とまでは行かないが、誰かを介せず意思の疎通ができることだけでも心苦しさが和らぐ。
三人寄れば文殊の知恵。まさか忍者の極意が役に立つ日が来るとは!お役に立てて拙者も嬉しいでござる、と感涙しながら深海からいい子いいこ、と頭を撫でられる仙石。うちの子供たちはこんな俺のために知恵を振り知り絞ってくれて…っ、目の端に涙を浮かべ息子の成長を見守る父親のような心持ちで眺めた。
一つ前進に向かったところで改めてライブの練習に入るようリーダーは促した。まずは柔軟に取り掛かる面々の後ろ姿を見ながらそれでも未知に対しての不安は消えはしない。
「…戻るよな、きっと」
ポツリと呟いた。その言葉は誰に聞かせる為のものでは無かったのだろう。独白はすぐそばに居た鬼龍にだけ聞こえたものだった。
「…そうだな」
と、返した鬼龍の言葉は守沢には届いていない。
-------------------------------------------
閑話。
一年ズに癒される。
2017-7-29 08:48
あんスタ紅千「皐月事変3」
前の記事へ
次の記事へ
カレンダー
カテゴリー
アーカイブ
- 2024年4月(1)
- 2024年3月(4)
- 2024年2月(2)
- 2024年1月(2)
- 2023年12月(1)
- 2023年11月(2)
- 2023年10月(3)
- 2023年9月(8)
- 2023年8月(1)
- 2023年7月(5)
- 2023年5月(3)
- 2023年4月(1)
- 2023年3月(13)
- 2023年2月(2)
- 2023年1月(7)
- 2022年12月(3)
- 2022年10月(3)
- 2022年9月(1)
- 2022年7月(11)
- 2022年6月(3)
- 2022年5月(15)
- 2022年4月(5)
- 2022年3月(1)
- 2022年2月(5)
- 2022年1月(3)
- 2021年8月(5)
- 2021年6月(3)
- 2021年4月(6)
- 2021年3月(4)
- 2021年1月(3)
- 2020年11月(2)
- 2020年9月(2)
- 2020年8月(4)
- 2020年7月(3)
- 2020年5月(2)
- 2020年4月(4)
- 2020年3月(5)
- 2020年2月(6)
- 2020年1月(1)
- 2019年12月(9)
- 2019年10月(1)
- 2019年9月(4)
- 2019年5月(2)
- 2019年4月(7)
- 2019年2月(2)
- 2018年12月(3)
- 2018年11月(1)
- 2018年9月(3)
- 2018年8月(6)
- 2018年7月(3)
- 2018年6月(6)
- 2018年5月(1)
- 2018年4月(8)
- 2018年3月(1)
- 2018年2月(9)
- 2018年1月(2)
- 2017年12月(13)
- 2017年11月(1)
- 2017年10月(7)
- 2017年9月(7)
- 2017年8月(3)
- 2017年7月(12)
- 2017年6月(5)
- 2017年5月(9)
- 2017年4月(9)
- 2017年2月(6)
- 2016年12月(4)
- 2016年11月(3)
- 2016年10月(8)
- 2016年9月(1)
- 2016年8月(1)
- 2016年7月(5)
- 2016年6月(7)
- 2016年5月(6)
- 2016年3月(14)
- 2016年2月(3)
- 2016年1月(1)
- 2015年12月(4)
- 2015年9月(12)
- 2015年8月(1)
- 2015年7月(1)
- 2015年6月(8)
- 2015年5月(10)
- 2015年4月(7)
- 2015年3月(4)
- 2015年2月(3)
- 2015年1月(1)
- 2014年12月(7)
- 2014年11月(3)
- 2014年10月(5)
- 2014年9月(8)
- 2014年8月(3)
- 2014年7月(1)
- 2014年6月(6)
- 2014年5月(1)
- 2014年4月(2)
- 2014年3月(5)
- 2014年2月(5)
- 2014年1月(2)
- 2013年12月(3)
- 2013年11月(4)
- 2013年10月(4)
- 2013年9月(4)
- 2013年8月(5)
- 2013年7月(2)
- 2013年6月(9)
- 2013年5月(3)
- 2013年4月(4)
- 2013年3月(6)
- 2013年2月(8)
- 2013年1月(7)
- 2012年12月(6)
- 2012年11月(6)
- 2012年10月(12)
- 2012年9月(7)
- 2012年8月(16)
- 2012年7月(8)
- 2012年6月(10)
- 2012年5月(8)
- 2012年4月(8)
- 2012年3月(7)
- 2012年2月(13)
- 2012年1月(11)
- 2011年12月(6)
- 2011年11月(12)
- 2011年10月(12)
- 2011年9月(5)
- 2011年8月(6)
- 2011年7月(10)
- 2011年6月(10)
- 2011年5月(12)
- 2011年4月(10)
- 2011年3月(7)
- 2011年2月(17)
- 2011年1月(8)
- 2010年12月(5)
- 2010年11月(11)
- 2010年10月(13)
- 2010年9月(2)
- 2010年8月(15)
- 2010年7月(10)
- 2010年6月(9)
- 2010年5月(8)
- 2010年4月(10)
- 2010年3月(15)
- 2010年2月(11)
- 2010年1月(24)
- 2009年12月(15)
- 2009年11月(22)
- 2009年10月(13)
- 2009年9月(10)
- 2009年8月(2)
- 2009年7月(18)
- 2009年6月(12)
- 2009年5月(5)
- 2009年4月(9)
- 2009年3月(13)
- 2009年2月(12)
プロフィール
| 性 別 | 女性 |
| 誕生日 | 6月14日 |