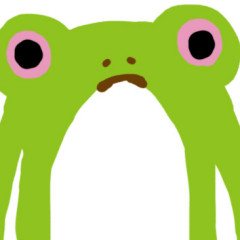ふざけるな、自己中、バカ、アホ、自分勝手、自由人、寝ぼすけ、不良、頭パー、女々しい、ハイテンション、甘党、幽霊、怨霊、呪怨モドキ、グロい、親友不幸(親不孝みたいな)………Etc.
阿実への悪態を散々並べながら、泣きそうに歪む紗良の表情。
涙こそ流していないものの、桂太と葵がそんな紗良を見るのはこれが二回目だった。
一回目は、イタリアへ行く阿実を空港まで見送った日。
「俺らのこと大好きとか言ってたクセに、何で離れてくんだよ‥っ」
二人はただ、黙って紗良の両隣に寄り添う。
あの日遠く離れて行った阿実は、冷たくなった姿で三人のすぐ目の前にいる。
(なー阿実。お前のだーい好きな紗良、泣いてるぞ?起きるなら一番タイミング良い今にしとけって)
桂太はすぐ傍にある存在を確かめるように、阿実の蒼白な頬に手を伸ばす。
しかしその氷のような冷たさに触れた途端、伸ばした手はあっという間に引っ込められた。
(今日は二人みてーに俺も甘やかしてやるからさ、冗談抜きで起きてくれよ…)
「額の傷さえ隠せば、まるで眠ってるみたいですね。…いきなりこんなの見せられて、阿実さんの死を受け入れろってほうが無理ですよ」
葵も阿実に手を伸ばし、眉間の穴を隠すように前髪を額の中央に寄せた。
その際指先が穴に触れそうになり、葵が肩を震わせたのに二人は気づかない振りをした。
「でも、残念ながらそれが真実です」
三人が開け放していた扉から、タイミングを見計らったようにリオが現れた。
その手には、鍵のついた少し厚い装丁の本を抱えている。
「か、栫井…?」
「貴方達がどれほど真実に近付けたのか、答え合わせをしましょうか」
本の鍵を外し、まるで生徒に質問を投げ掛ける教師のようにリオは言う。
リオは阿実の死体を挟んで、三人の正面に腰を下ろした。
「この本…いえ、阿実サンの日記はこう始まっています。
『紗良と桂太と葵に、いっぱいいっぱい嘘を吐き続ける日々は終わった。』
…と」
彼は詩でも朗読するように、静かに語り始めた。
嘘から始まる
(それは、信じられない答え合わせ)
2011-3-9 15:55
カレンダー
<<
2024年05月
>>
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
プロフィール
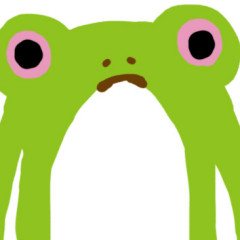
| 性 別 |
女性 |
| 年 齢 |
29 |
| 誕生日 |
10月30日 |
| 地 域 |
栃木県 |
雑記
【年間アクセス解析】
2015年 合計アクセス:集計中
2014年 合計アクセス:10521
2013年 合計アクセス:10029
2012年 合計アクセス:2890
2011年 合計アクセス:11773
2010年 合計アクセス:27347
【パスワード】
病み・黒歴史は私の誕生日4桁
王国心夢は異端の印を4回連続
夢主の名前は基本的にアミで固定です
ごめんなさい