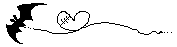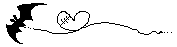今朝の夢を覚えてるところだけでも文章にしてみた(´・ω・`)
長い廊下から見える外の景色を眺めながら、3人の少女は歩みを進めた。案内人はこの家の主の姉――紫堂縁(シドウ・ユカリ)だ。
「見えますか?」
「いや、私には……」
「うん、何も見えないよ」
縁の問い掛けにふるふると首を振る。
「そうですか……」
「え……何、あれ」
前方から震える声がした。茶髪のショートカットの少女が口元を手で覆いながら目を見開いていた。
隣にはその少女を支えるようにして立っている背の高い少女。
どうやら先客がいたらしい。
私たち以外にも依頼しているのか。
少女の傍に駆け寄り、外を見る。
ああ、なるほど。
本当に――いた。
うらめしそうにこちらを見下ろしてくる大きな顔の女。
『呪い』か『怨念』か。
どっちにしろこれが今回の標的だ。
私たちに見えなかったということは、何かしらのフィルターがかかっているということで。
こいつら雑魚ににそういう器用な芸当はまずできない。
――どこかに黒幕が潜んでいる。
「トイレは大丈夫?」
「ん、行ってくる」
ふたつめの扉が開き、また長い廊下が続いている。
段々とうんざりしてくる。
そして何故こんな中途半端な場所にトイレがあるのか。
不思議に思いながらも、とりあえずトイレ休憩だ。
縁はさっき出会った少女と話をしている。
青ざめていた顔色もだいぶよくなっていたので安心だ。
あれから暫く歩いた。
途中途中で同じように依頼を受けたらしい人々に会った。
悲鳴を上げる者、気絶しているもの、泣きじゃくっている者など。
反応はそれぞれで。だが、見えているものは同じだった。
その側に行けば上手く同調することができ、邪魔なフィルターもかからないことに気付いた。
「私ほどアメショが似合う者はいませんよ」
縁が上品に笑う。
いや、そんなことは誰も聞いちゃいないのだが。
庭には無数の珠が転がっていた。
数珠を解き、ばらまいたのだろう。
だが、それに何の意味があるのか。
疑問に思わざるをえなかった。
金髪のツンツン頭の青年が、濁った瞳でこちらを見てくる。
「数珠の3番を君に捧げよう」
そう言って、青年は歪つな形の珠でできた数珠を辺りに散らす。
その光景に見とれているうちに、青年がすぐ傍に歩み寄ってきていた。
その手に持っている珠が『3番』らしかった。
歪つな形の珠しかないと思っていた先程の数珠に、こんなに綺麗な珠があるとは思わなかった。
「私も何回も試したんだがね。一向に効果が現れないのだよ」
この庭の所有者であり、今回の自分達の依頼主――紫堂義丹(シドウ・ギタン)が苦笑混じりに言い放つ。
濁った瞳の青年は気にした様子もなく。僅かに口角をあげ、その手に残っていた『3番』の珠を緩慢な動作で手放した。
まるで、スローモーションのようだった。落ちていく珠が、地面に落ちるまでの時間がひどくゆったりとしていたのだ。
ちゃり、という地についた音がしたと同時に、どろりとした空気が辺りに満ちた。
やばい、と思った瞬間には時既に遅し。
オレンジの群れがどこからともなく現れた。
「それ以上近づくな!」
群がるオレンジの修道服の男たちを回し蹴で蹴り倒し、明らかに自分より体重があるであろうそいつらを、軽々と持ち上げ広い庭目がけて放り投げる。
すでに人間ではないのだから、これくらいで死ぬわけがない。
だが、これらを滅するのは下にいる仲間の仕事。
自分はこの場所を守ることに専念するだけ。
後のことは、下に任せるしかない。
自動ドアのガラスの向こうに、アメリカンショートヘアーが数匹見える。
自分の足元には黒い猫。
大切な、パートナー。
ポニーテールを揺らしながら、少女は男たちを凪ぎ払う。
翻るスカートから覗くすらりとした足。その足で、鋭い蹴りを繰り出す。
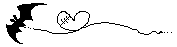
中途半端。
ってかどういう夢だ(笑)
前にも同じの見たんだよな。
何なんだろ。