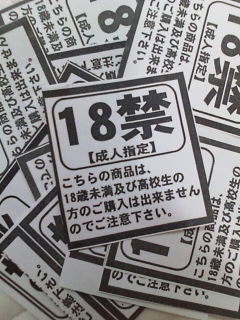王は一人自室にいた。
北の王にずけずけと本当の本当の言われ、しかも要もいなくなってしまい、意気も消沈し、あの一見の後一人部屋に引きこもってしまった。
「所詮私は王の器ではなかったということさ。」
一人そう愚痴てみるが、それに応える者も叱り飛ばす者ももういない。
誰よりも傍にいて、誰よりも王を慕い、誰よりも王を思ってくれた存在はいない。
「名前、まだ教えてなかったのにな。」
王の名は、王の親か、王の妻にしか教えられない。それほど特別なものなのだ。きっと要に教えたところで、要は名前の本当の意味など知らず、いつものように“あいつ”と呼ぶだけかもしれない。それでも、今こんなにも悔いを残すのなら、正直な気持ちを打ち明けるべきだったのかもしれない。
「名前、教えてくれるの?」
ふと聞こえたのは耳になじんだ声。本当ならば聞こえるはずはない声。思わず振り返ると、そこには帰ったはずの要がいた。
「お前……帰ったんじゃないのか?」
そこに存在するのが信じられなくて、思わず近づいてその腕を掴んだ。しかし王の思いを裏切り、要は確かに存在していた。
「まさか、北のが嘘をついたのか?」
そうすれば辻褄が合う。恐らく北の王が今回の計画をし、家臣たちもグルになってやったことなのだろう。カッと怒りが湧き、そのまま北の王の元へ駆けようとすれば、今度は要が南の王の腕を掴んだ。
「待って!」
要の目はどこか涙ぐんでいて、元いた世界に帰れないのではと絶望していた姿以来の彼女の弱々しい姿だった。
「名前、教えてくれないの?」
恐らく要は名前の意味を知ったのだろう。
もし今までの王だったら、また彼女をからかうようなことを言って、誤魔化すかもしれない。でも今は、こんなにも素直に思いが伝えられる。
「朱劉(シュリュウ)だ。」
「そう、朱劉。」
そう名前を呼んでくれた要の傍なら、自分は素直に生きている気がする。
王は満ち足りた思いで、要を抱きしめた。
.