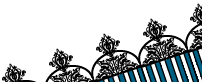堕 楽
堕 楽
2012/07/09 19:35
:SH
 ツイッターSSログまとめ11
ツイッターSSログまとめ11
リクエストいただいたものとかいろいろ 長め
****
【現パロイドテレゼ】
とんとん、とプリントアウトした書類を揃えてクリップで留める。明日の会議で使うものだ。「あら、こんな遅くまでお疲れ様」不意に開いたドアを見遣ると、黒髪の女性が顔を出していた。視界の端に見えた壁掛け時計が指すのは午後10時、大方同じ立場だろうと察するのは容易い。
「今帰りかい?」「えぇ」今月もなかなかいい額の残業代がつくだろうな、と自嘲気味に笑うのにも慣れた。出るだけマシだと憤っていた友人もいたけれど。「送って行こうか、少し待っていてくれたまえ」夜道は危険だし、この時間は電車の本数も減ってくる。パソコンの電源を落とし、立ち上がった。
「有り難いわ」まさかそれが目当てで顔を出したのでは、と訝しむのはやめにした。どうせ家は通り道だし、もっと言えばそれでも構わないと思っている節があったから。彼女はしたたかだが、そこが魅力でもある。車のキー、財布、携帯。タイムカードを押して電気を消して、職場を後にする。
「遅い時間だけれど、夕食でもどうだい?」眩しいほどのヘッドライトにネオンサイン、安っぽいカーラジオ。助手席の横顔は、振り向いてくれることすらしない。「やめておくわ、明日も早いのよ」のらりくらり、行方知れずのウインカー。素っ気ない帰り道は、なにも初めてのことではない。
「残念だよ」なら次の週末は、そう言いかけてやめた。きっとまた理由をつけて断られてしまう。このままの関係で十分という言い訳に、傷付くことを恐れているのかとエゴが嘲笑う。「ごめんなさいね。それじゃあ」停止した車、開くドア。軽い礼の言葉だけを残して、彼女は男の前から消えていく。
嗚呼、そのスーツの袖を掴んで引き留めることが出来たなら。幾度重ねたか分からないその感情を彼が本当に後悔するのは、もっとずっと先のこと。後ろ姿を夜の帳に見送って、車は再び走り出した。 (君はいつもそうやって、私の前から消えていく!)
【メルエレ】
「やぁ、死に損ない」笑みの形を浮かべる黄金の瞳はしかしまさに形だけで、声色は冷たかった。はぁ、とエレフは嘆息する。「お前には言われたくなかった」宵闇色の髪の下で、血の気の無い皮膚がぴきりと皹割れる。元より屍体の身は、今や壊れかけたマリオネットに近かった。
両腕に抱いた少女人形も、そのお喋りだった口から美しい顔までを朽ちさせて、真っ暗な眼窩でエレフを見詰めていた。「ふふ、悪いねこんな姿で」道化のような仕草で彼が肩を竦めた瞬間、宵闇の森が戦慄いた。壊れた唄は悲鳴に変わり、明けない夜を蝕んでいく。その先にあるのは、終焉だけ。
「……消えるのか?」ざわざわと震える空を見上げて、呟く。物語の終わりはいつも呆気ないものだと、一度本を閉じてみれば分かるのだけれど。「またやり直すだけさ。出来損なった童話を壊して、七の地平は廻るだけ」そう語る声すら、少しずつ雑音へと変わっていく。その時はもう近いらしい。
「じゃあさよならは無しだな」けれどエレフはそう言って少しだけ笑った。衝動の演者ではない彼は、世界が消えても存在し続ける。また待てばいいだけのこと、そう言うと屍体も渇いた唇を少しだけ吊り上げた。「そうかもしれないね」「あぁ、待っててやるよ。お前が戻ってくるまで」
再会のその時にまた、大罪を孕んで屍揮者が笑うだろう。低く囁く甘美な死の唄を思って、エレフは一度消え行く地平を見つめる――黒く染まった髪を、掻き上げながら。 (そして冥闇が童話を包み、死神は優しく頁を捲る)(其れこそが繰り返される悲劇だったとしても、堕ちるだけ)
【メルイド】
「―――――」はく、と開いた色のない唇から零れたのは吐息だけだった。「どうした、メル」ぱくぱくと口を動かす滑稽な仕草を幾度か繰り返して、ぽろりと黄金の双眸から涙が落ちた。「メル!?」「……言えないんだ。君に伝えたいことがあるのに……言葉に、できないんだ」
(それは青年を縛る、魔女の鎖)(私以外ヲ、愛スルナンテ)
【イヴェタン×シャイタン】
紅と蒼のオッドアイ、覗き込む容貌は見慣れた冬の子供と同じなのだが――彼はこんな表情を、しない。「Shaytan?」若干のフランス訛りを残しながらも、しかし名を呼ばれたのはもしかして初めてではないかと。不意にどくりと心臓が五月蝿く鳴って、つい顔を背けた。
【メルアメ】
死人戦争ねぇ、とメルヒェンは肩を竦めた。「神を殺し、死を植え付けて。君達はこの世界を滅ぼすつもりかい?」冥府の底の闇の中、昏い視線のその向こう。黒い髪に紫の瞳、青年の名はアメティストス。「ミーシャのいない世界なら、消えてしまっても構わないさ」
復讐を携えた黒き刃に、鉄錆の匂いを纏わせて。唄を見守る屍揮者は、愉しげに口角を上げる。「でも君自身だけは決して死なない。君はタナトスそのものになったのだから」死を志向する衝動が、二人を地平の彼方で結び付ける。幻視するのは焔無き、荒廃した無限の大地。
「お前とて、そうだろう」狼はそっと牙を剥く。生命の残骸と化した屍体を積み上げて全てを壊しても、メルヒェンはその中にはいない。もう死んでいるから、奪うものなどないのだ。確かに、と色のない唇が笑う。「ならその世界には、私と君の二人きりだ」
自ら闇の底へと堕としたかつての楽園を見て、彼は何を思うのだろう。喪われしものはもう、戻って来ないと気付いている。「二人きりで何をしろと言うんだ」終焉を、知りたいだけなのかもしれない。唄だけが、頁を誘う。「そうだな、恋でもしようか」「……恋?」
壊れたディストピアで、まるでアダムとイヴのよう。知恵の実を探して、罪を犯すのも悪くはない。裁く神など、殺したあとなのだから。「君が奪ったこの益体もない世界で、私は君と恋をしたい」悪魔が囁くようにメルヒェンは嘯く。アメティストスは返事をせずに、ただ、笑った。
"絶望オーケストラ" (さぁ踊ろう!この身が朽ちてしまうまで!)
【メルテレゼ】
夢を、見た。眠らない屍体に夢というのも可笑しな話だが、ともかく夢を見た。見覚えのある風景に、立っていたのはひとりの女性。顔はよく見えなくて、ただ髪に飾った青薔薇がやけに目についた。『いいかしら、メル。もし私が死んでしまったら――』
台詞の続きは、思い出せなかった。あれは誰なのだろう?どうして自分の名前を?そんな疑問が、ぐるぐるとメルヒェンの頭を回る。それよりなにより、私が死んだら、とは。何故彼女がそんなことを自分に言うのか、残念ながら想像もつかない。まして彼女が今生きているのかどうか、など。
死んだら、どうしろと言うのだろう。燃やして灰にしてくれ?財産をどうこうしてくれ?有り体な遺言を指折り数えて並べてみても、しっくり来ない。不快なもどかしさに、つい親指の爪を噛む。瞼の裏に霞む青薔薇の鮮やかさが、憎らしくすら思えた。そもそも何故、気にする必要があるのかと。
綺麗さっぱり忘れることだ。やがて自我が賢くもそう諦めて、メルヒェンはそれきりそのことについて考えることはしなかった。実際一度きりの夢を忘れることは容易く、最後の最期まで彼がそれを思い出すことはない。
――いいかしら、メル。もし私が死んだら、貴方は私を忘れてしまいなさい。 (賢女の望んだ歪な奇跡と、魔女のささやかな祝福と) (ムッティ、そんなかなしい約束、守りたくなんてなかったよ)
【屋根裏ロマン】
ギシ、ギシと一歩ずつ、階段を登っていく。朽ちかけたそれは今にも踏み抜けそうなほど脆く見えたが、不思議とその均衡を保っていた。――まるでこの、地平のように。 しん、と静まり返った空間には、なにもない。ただこの階段と、イヴェール自身の他には。
否、階段の向こうには何かがあるのかもしれない。未だ視認出来ない空間は其処だけだ。あとはぽっかりと広がる黒い虚無にも、五感を遮る白い霧にも思える不毛の世界。ギシ、また一段足を進める。生のざわめきも死の笑い声も、此処にはない。ひとりぼっち。けれど自らこの結末を、選んだのだ。
生まれてくる朝の為には、必ず死んでいく夜が伴う。廻り巡る焔の摂理は、遂にイヴェールを逃がしはしなかった。彼が存在するに至る物語は、確かに在る。けれどそれは、痛み無しには有り得ない。即ち子を送り出すのと引き換えに、病弱な母は命を落としてしまう。そんな哀しい詩が、伝言の真意。
許せなかった。迷えなかった。母が子の幸せを願ったように、子もまた母の幸せを祈る。冬の骸は、自らの物語を断つことを選んだ。後悔など、していない。「ごめんね、ママン」賢者が代わりに囁いたのは、終末へ至るもうひとつの伝言。それに導かれて、イヴェールは此処までやってきた。
終焉の幻想。その正体は、【彼女】が屋根裏で描いた夢。紅い衝動に招かれて、遂に最後の一段を登る。そこから見下ろす階段の向こうには、折り重なって死んだ少年達の屍体。誰でもあって誰でもない、【Laurant】の慣れの果て。そして頭上から吊り下がる、環状の細いロープ。
階段は十三段。約束された絞首台。凶器はやがて朽ち果て屍体は垂直に落ち、彼は十三人目の少年となるだろう。そうして生まれ堕ちる、狂気の名は。「ありがとう。さようなら」そっと、夜に似た虚空へ足を踏み出す。ギシ、と軋んだのは一体誰の心か。目を閉じて呼吸をやめれば、扉は開かれる。
こうして物語は、また新たな歴史を紡いでいく。憎しみ廻る地平に、幾つかの詩を灯しながら。 (僕は此の世界を、愛していました)
bkm
←
 →
→

 堕 楽
堕 楽
 ツイッターSSログまとめ11
ツイッターSSログまとめ11
 →
→