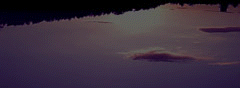|
|
ログイン |

(離れてから、気づいたんだ。当たり前で、大事なこと)
(夢を追う君に、見守る僕。見つけた流れ星にはきっと違うことを願っていた)
(そんな君に僕ができるのは、たった一つだけ。でもきっとそれは、僕らにとって、なによりも大切なこと)
森は深い夜の静寂につつまれていて、月明かりだけが白々と光っておりいかにも幻想的であった。
このような空を見上げて綺麗だね、と笑い掛けてくる少女も今はもう隣にはいない。この場所でロイドを囲むのは旅の仲間ではなく、夜の森の薄暗い静けさだけだった。寒さに負けて体がぶるりと震えた。吐く吐息は白く、もうこんなに寒い時期になったのかとロイドは赤くなった指先を見た。
ロイドはその赤くなった手をぐっと握りしめた。クソッ…! と無意識のうちに言葉を吐き捨てた。彼の胸のうちに後悔や懺悔、やるせない無念さが込み上げる。
素手のまま、ロイドは目の前にそびえ立つ樹に拳を突き出した。
「あいつには…!」
こんな冬の寒さを感じる感覚さえない。
「………な、にが。なにが俺が守ってやるだよ…。おれ……俺はあいつの何を背負ってあげれてたっていうんだよ」
なにも背負ってやれなかった。彼女の嘘も、苦しみも…それに気づいたときにはもう遅かった。戻れないところまで来てしまっていた。だから、だからせめて
「なぁ…コレット。俺は…お前の夢だけは叶えてやろうって。どれだけ苦しくても、辛くても笑ってるお前を支えてやろうって」
樹に触れていたロイドの拳に赤い血が滲んでいた。ロイドは鈍い痛みに眉を寄せたが、それを樹から離すことはしなかった。
「…みんなが幸せになるんだって」
目を閉じれば浮かんでくるのは彼女の笑顔ばかりで、そしてそれとともに思い出すのは、救いの塔での、最期の言葉。
『私、ロイドがいたから、この世界を守りたいって思えるようになったんだよ』
やめてくれ。そんなの有り難くも嬉しくもないんだ。そんなこと言わないでくれ。頼むから!
みんなが幸せになるように世界を再生するんだよって俺に教えてくれたのはお前だったじゃないか。俺と船旅しようって約束したのは嘘だったのか。
ロイドは自らの手を後ろに引くと、もう一度樹に向かって突き出した。
なぁコレット。みんなが幸せに…ってさ、お前はよく言ってたじゃないか。そのみんなにお前は含まれてないのかよ。それって…それっておかしいだろ。
お前は、俺がお前を犠牲にしてまで再生される世界を喜ぶだなんて本当に思ったのか? 俺が…そんな世界で―笑っていられるって、思ってたのか?
そうだとしたらコレット…お前は間違ってるよ。……俺はそんな世界なんて望まねぇよ。
『君に伝えたい言葉』
「どしたの?」
仲間たちから離れて、成人男性くらいの大きさをした岩の裏で地べたに寝そべっていたロイドにコレットが覗き込むように声をかけた。
「わっ!」
くわっと大口を開けたロイドは短くそう吠えると、コレットの反応を待った。
「わっわわわっわ…」
コレットは、どこか落ち込んでいるように見えたロイドに威かされて、びっくりして飛び退いた。そのまま後ろに重心が傾き、体がぐらりと揺れる。
宙を舞ったその手首を、コレットよりも幾分も温かい手がしっかりと握った。
「きゃっ…」
ぐっと手首を引っ張られ、コレットは勢いよく前に倒れ込んだ。
ロイドの胸に飛び込むようにして彼に覆い被さってきたコレットの背に手を回して、その体を支えてやる。
「あっぶねーっ! コレット、大丈夫か!?」
ロイドはなかなか顔を上げないコレットに、怪我をさせてしまったのかと不安になった。
もぞり、とコレットがロイドの上で寝返りをうつ。
「………だいじょぶだよ」
その姿勢のままロイドに微笑み、ただ静かにそう告げる。
なかなか退こうとしないコレットにロイドは回してしまった手をどうすればいいのか分からなくなった。……強く握っている、手首も。
周りの夜の静けさに飲まれてしまったかのように、二人の間を沈黙が流れる。
「あったかいね」
「え?」
ややあって、沈黙を先に破ったのはコレットだった。その顔をまじまじ見れば、どこか赤らんでいる。
「ロイドとこうしてると、すごく温かいの」
嬉しいなぁ、とふわり微笑んで見せる。
「そうか? コレットが冷たすぎるんだよ」
手首から伝わってくるひんやりとした感触が、コレットの体温の低さを物語っていた。
「こんなに冷たくて大丈夫なのか?」
「えーだいじょぶだよぉ。えへへ」
コレットは頬をすりすりと、離れるのが惜しそうに赤色の服の上で滑らせた。ロイドは驚くと同時に己の体温がぐうっと上がるのを感じていた。
「…うん。ありがと。ごめんね」
長居しちゃった。舌を出して照れ笑いを浮かべつつ、コレットがロイドの元から離れた。と、同時にロイドの手から彼女の手首が解かれる。
「いや、いいぜ。それよりコレット、大丈夫か? 怪我とか…」
「だいじょぶだいじょぶ! ね? 血だって滲んだりしてないし」
「本当かぁ? そう言ってて騙されたことがある気がするけどな」
それは過去と呼べるほど昔のことではない。ほんの数ヶ月前の話だ。
幼い頃から聞かされていた神子様の世界再生のお話。コレットの世界再生の旅に半ば無理矢理ついていって、旅を進めて、救いの塔に行って………そして死ぬほど後悔した。
「あ………あれは、その。ごめんなさい」
眉を下げ、悲痛そうに顔を歪めたコレットを見て、ロイドは自分の言った言葉の鋭さにはっとした。
「あ、ごめん。コレット。そんなつもりじゃなかったんだ…。コレットは誰よりも頑張ってて…悪いのは俺だよな」
ずっとなんの根拠もないくせに、コレットはコレットだ、なんて言い続けて。嘘ばかり吐かせて。
ロイドはそう言葉を濁らすと、唇を噛み、それから固く閉じた。ぐっと擦り押した地面がじゃらりと音を鳴らした。
「…どうして、ロイドが謝るの? 私にいつも謝るなって言うのはロイドだよ。だからほら、ロイドもそれ以上自分を責めないで」
悔しそうに地面を踏みつける赤いブーツを見、コレットが手を組んだ。祈るように、願うように…そして懇願するように。それは…優しい彼がこれ以上自らを責めないでいいように。
「でもさ、俺…お前…いや、コレットのこと守るなんて言って…結局なんの力にもなれてなかった」
「そんな…!」
コレットは自分の耳を疑った。あり得ない、と。
「どうしてロイドはそんなこと言うの? 私は、ロイドがいたから!」 コレットは声を荒げ、ロイドの方に身を乗り出した。そして、彼のどこか悲しそうな目を見ると、唾を飲み込みはっとしたように伏せ目になって続けた。 「…ロイドがいたから、16年間生きて、これたんだよ」
最後のほうは涙声になっていて、その声にロイドはひどく情けない気持ちになった。違うんだ、コレット。そうじゃなくて。
「俺がいたから、なんて言うなよ」
その言葉が、重いだなんて、とても悲しいだなんて…そんなことコレットに言ってはいけないに決まっている。俺にはそんな資格はない。
それなのに、どうして、言葉は口から溢れてしまうのだろうか。ロイドがダメだと、自制をかけようとしたときにはもう次の言葉が口から吐き出ていた。
「コレットはコレットだろ。みんなの幸せっていったいなんなんだよ。俺が、俺がお前に、いったいなにをしてやれてたって言うんだよっ!」
「ロイ…」
コレットがなにかを言おうとした。しかしそれさえも待っていられなかった。感情をただただ吐き出すかのように言葉が次から次へと止まらない。
「なあ、コレット。俺は、俺はそんなに頼りにならないか? ずっとずっと嘘を吐き続けなきゃいけないほど―俺は」
今、手に持っていないはずのあのホットコーヒーの温かさがかじかんだ指に戻ってきた気がした。あのときと同じように、いや、より近くで、コレットが怯えたように…ひどく寂しそうに眉を歪め、そしてそのまま口元だけの笑みを作った。
ことん、と、聞こえないはずのマグカップの落ちる音まで、聞こえた気がした。
「俺は、お前がそう言ったとき、すげえ悲しかったよ」
あんなに血の気を失ったコレットの顔を見たのは、二度目だった。一度目のとき、コレットは涙さえ流せないと言った。俺があんなにも畳み掛けるように、彼女を責めるように言ってしまったのにも関わらず、だ。
二度目は、今。
眼前にいるコレットは愛想笑いを浮かべることも忘れ、ただただその瞳を大きく開いて…息さえ止めているようだった。
「…っ…あ、そ…れは」
震えた声は言葉にならず、コレットはただゆっくりと、ロイドから離れ、がくんと足から崩れ落ちた。
コレットとしても、それは予想できないことではなかった。自分がいるからこれまで生きてこられた、と、自分がいるから死ぬ覚悟もできた、と…そう言われて、嬉しい人がいるだろうか。いない。私なら、きっと。
「ごめんなさい…、ごめ、私、ロイドに…酷い、こと」
私の、所為だって。その人が、死んでしまったのは私の所為だって…そんな風に、思っちゃう。コレットは自分を否定するかのように、ぎこちなく首を振った。
「でも、でもね、ロイド。私が今、生きてるのは…今、こうしてロイドに謝れるのはね、ぜんぶ、ぜんぶ…ロイドのおかげなんだよ」
ここで引き下がるべきだ、ありがとうと、ロイドはコレットの言葉を受け止めるべきだった。
「おかげって…違うだろ! 俺はまたお前を苦しめてる。ぜんぶお前が背負ってる。―俺が」
コレットの泣き顔を直視したまま言うことは到底できなくて、地面に視線を落としてそれから、離れたところで盛り上がっているみんなにも聞こえてしまうほど強く、最低な言葉を吐いた。
「コレットを、嘘つきにさせたんだ! 再生から逃げ出したなんて―コレットが言われる羽目になったのは俺の所為だ。コレットを取り戻すなんて張り切って、その所為で―」
俺は、こんなことをコレットに言って、なにがしたかったんだろうか。これじゃあまるで、コレットが再生から逃げただなんて喚いている輩となにも変わらないじゃないか。
話題を変えなくては、コレットを笑わせてあげたいのに。俺はなにをしているんだろうか。俺はまた間違ったのか?
ロイドはどうすればいいのか分からなくなってしまい、そのまま黙るしかなくなった。
ほどなくして、リフィルとジーニアスを筆頭に仲間全員が飛んできた。駆けつけたリフィルの表情はとても険しく、話を聞かせてくれるかしらと、ロイドを引っ張りつつ野営のために張ったテントへ向かっていった。
「…コレット、大丈夫?」
ジーニアスがコレットの顔を下から覗き込むようにして伺うと、涙を目にいっぱい溜めたコレットがいた。そして、その唇が、ごめんなさいと小さく動いたのを彼は見逃さなかった。
「コレット! あんたが謝る必要はないよ! まったく…ロイドのヤツはなに考えてんだい!?」
しいながその横で地団駄を踏んだ。かんかんに怒っているようで、拳を握っている。そして、軽やかなステップでコレットの肩に手を回したゼロスが続けて言う。
「かわいーいコレットちゃんを泣かしちゃうなんてロイドくんも罪な男だなぁ〜? コレットちゃん、今からでも俺に乗り換えない?」
「アホ神子! バカなこと言ってんじゃないよ!」
空気の読めてないゼロスの発言にしいながつっかかった。が、あえて空気を読まなかっただけなのだろうと察したジーニアスは、今回ばかりはゼロスに同調しながら消えていく赤色の背中を見送った。
「…コレットさん。大丈夫です。ロイドさんが、あなたのことを嫌うわけないです」
プレセアが口にしたことはたしかに正論で、それはコレット以外には分かりきっていることなのだが、お世辞にも今のコレットにその言葉が届いているとは思えなかった。
とにかく、コレットを休ませて、落ち着かせてあげないと。でなきゃ、このままずっとここで謝り続けている気がする。
そして―。あのバカロイドは姉さんにみっちり説教されるだろうから、ちょっとはフォローしてあげなきゃ。コレットに肩を貸して歩くゼロスとしいなの後を追いながら、ジーニアスはそう考えた。