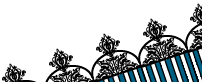堕 楽
堕 楽
2012/07/30 18:07
:その他版権
 絶望讃歌(言時)
絶望讃歌(言時)
Fate/Zero、修業時代のマボワ
****
意外と言えば意外だったし、似合っていると言えば似合っていた。
広い遠坂邸の片隅に、ピアノがあるのは知っていた。流石にグランドサイズでは無いけれど、しっかりとした造りのものだ。しかしこれまで誰かが弾いているのを見たことは無く、埃こそ被っていなかったが半ば物置になっていた。
その蓋が今は開けられ、流麗な音色を奏でている。
綺礼は音楽に造詣は深くない。曲名も知らないし、またその旋律を美しいと思う心も持ち合わせていない。ただはっきりしているのは、弾き手が遠坂時臣であるという、見れば誰でもわかることだけ。
人の気配に気付いてか、長い指が動きを止めた。振り向く碧眼に、いつもの柔和な笑み。
「綺礼、」
声くらい掛けてくれれば良かったのに、と時臣は苦笑いを浮かべた。邪魔をするのも悪いように思えたし、そもそも今来たところなのだからその台詞はやや理屈を誤っていたが。
柔らかな音色が途切れれば、部屋は静かだ。母娘は外出でもしているのだろうか。
「ピアノ、弾けるんですね」
綺礼は率直な感想を口にする。名家の跡取りという表現を使うと、なるほど嗜みとして不思議はない。だがその一方で、魔術一辺倒だと思っていた師にこんな趣味があるとは想像もしていなかった。
上手い下手はよくわからないが、少なくとも並以上の腕だと思う。そこらで流れているクラシックと比べて、素人耳に遜色は無かった。
「齧った程度だよ。才は無かったし、もう何年も触っていないからね」
才の平凡さを努力で補えるのが時臣の才だと璃正は評価していたし、綺礼も強ち間違いではないと感じている。齧ったと言っても数年は練習に励んだのだな、という予測は用意に立てられた。
自転車と同じで、一度出来るようになれば身体が覚えているものだと聞いたことがある。ちらと見る限り楽譜らしきものは無く、嘗てよく弾いた曲なのだろう、と。
「私には十分な技量だと思えましたが」
「ありがとう」
音楽に限らず絵画など芸術の類は、上手い下手よりも好き嫌いで感想を述べたほうが好まれる節がある。けれど生まれてこの方そんなものとは無縁に育った神父にはそれが理解出来なかったし、時臣も敢えてどうこう言わなかった。
教会のミサで使われるパイプオルガンとは趣の異なる音色。綺礼とて、悪い気はしない。
「もう少しだけ、弾いてもいいかい」
「えぇ」
工房で待ち合わせた時間には、実際まだ早かった。几帳面に早く行動した結果であって、急かす理由にはならない。
指が再び鍵盤に触れる。聴衆のいない、演奏会。
先程までの曲は緩やかで朗らかな印象を与える旋律だったが、今度は違った。激情的で衝動的で、切ない。音楽知識に長けた人間がもしこの場にいたら、長調と短調の違いを教えてくれただろう。
暗い和音をなぞっている瞬間すら、時臣の手つきは優雅だった。およそ真似出来そうもないその動きをぼんやりと眺めていた綺礼はふとあることに気付く。
主旋律を鳴らす右手が、黒い鍵盤ばかり辿っているのだ。それの意味するところを理解出来るだけの知識も感性も無いから、どうということもないのだが。
短い曲だった。悲劇が流転するように駆け抜ける曲だった。大きな変化も持たぬまま、音が勢いよく堕ちていくような。
そして時臣は拍手もせずにぼうっとしている弟子を振り仰ぐ。
「この曲は、綺礼に似合うなと思って」
お気に召したかな? と尋ねる笑顔に、ぞわりとしたものを感じる。
さっきの眠たげな曲よりは確かに好みだ。でも、そうじゃない。
調和している筈なのに、絶望に似たハーモニー。死の舞踏を嗤うように鮮やかなメロディ。
――このひとはどこまでわかっていて、言っているのだろう。
夢見がちな理想主義者、永劫理解しあえない人間。そんな時臣に対する認識を改めねばならないの、か。
深層に眠る悪魔。死にたくなるほど歪んだ世界。重ね続けた嘘。魔術師を殺す、この武器の、名前は。
「……ありがとうございます」
表情を動かさずに、口先だけの礼を述べるのが精一杯だった。
無意識なら無意識で、気付いているならいるで、恐ろしい。綺礼は時臣が怖いと、初めて感じた。
嗚呼。
でも同時に。
あのピアノは悪くなかったと、思ってしまったから。
また聴かせてください、などと唇から滑り落ちた言葉はほぼ本心だ。得体の知れない恐怖を振り払うために、綺礼は工房へと足を向けた。
絶望讃歌
(響いていく、声なき声)
bkm
←
 →
→

 堕 楽
堕 楽
 絶望讃歌(言時)
絶望讃歌(言時)
 →
→