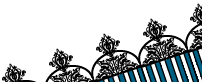堕 楽
堕 楽
2012/06/23 16:09
:SH
 嘘吐きとイデアリズム(童話航海士)
嘘吐きとイデアリズム(童話航海士)
メルイドっぽい気がするサムシング
****
"この地平に、雨は降るの?"
何時だったかふらりとやって来た冬の子供にそう問われたことを、メルヒェンはふと思い出す。
答えはJaだ。
時の感覚は無いけれど、井戸底から見上げた雲の形は移ろいゆくもの。
ごく稀にではあるが、雷鳴が宵闇の森を照らす幻想的とすら言える光景に巡り会えることもある。
尤もそれが紡がれる童話の舞台として相応しくない限り、頁に綴られることは無いのだけれど。
「雨と言うより嵐だな、これは」
そんなぼんやりとした思索を、回想ではなく現実の声が遮った。
意図せず下ろしていた瞼を開けば、肩を竦める金髪の男の姿。
翡翠の瞳が映す円い夜空から、しかし雨は落ちてこない。なにせあまりにも横殴りで、風の音が五月蝿いくらいなのだ。
「船だったらとうにひっくり返っていそうだね」
独り言のようなその台詞に、イドルフリートが静かに口角を上げた。
当然ながらメルヒェンは、意図的に言葉を選んだのだけれど。
「……偶には外に出てみないかい、メル?」
普通の人間ならば正気の沙汰ではないだろう。しかし所詮彼等の肉体は、呼吸をし鼓動を刻むそれとは大きく異なる。
風邪をひくどころか、願えば一滴も濡れないことすら、この【モリ】の中でなら可能となる。
しかし敢えて外へ、と言ったイドルフリートはこの荒天を肌で感じるつもりだ。そうでなければ意味がない。
「構わないよ」
そして二人の器がそうであるように、この井戸も半ば概念存在だ。
浅く湛えた水がいつも復讐劇に繋がるように、無限に続くとすら思える深い深い奈落の底すら、星に手を伸ばす程の天頂と何ら大差ない。
主が命じれば、如何ようにもその境界の彼岸を変える。
瞬きひとつの間にもう、メルヒェンは井戸端に立っていた。
「これは凄いな」
その隣でイドルフリートは目を細める。けれどその横顔はやはり笑っていた。
飛ばされそうなほど吹き荒ぶ風、敵意さえ覚えるほどに狂暴な雨。
こんな様子では魔女も林檎を売りには来ないし、王子様も迷いの森を抜けられないだろう。
お伽話の舞台には、およそ似つかわしくない。
もっと異なる物語、そう、例えば冒険奇譚であるとか。
「ここまでの嵐は初めてかい?」
右に倣えで濡れるがまま、メルヒェンはイドルフリートに問い掛ける。
嘗て彼が船乗りだったと、いつ知ったのかはもう忘れた。
あっという間にべたりと顔に張り付く髪、重くなる上着。
そんな状態でも愉しげな表情を崩さない理由に、一抹の興味が湧いて。
「いいや。もっと酷い思いだって、したことがあるさ」
その身体が過去に歴史を生きていた頃、航海士としてこんな風に振る舞っていたのか。
残念ながらメルヒェンに、それを確かめる術はない。
挑戦的で、挑発的で、好戦的。
摂理を裏切るに足るほどの傲慢。
「ふぅん? では何故わざわざ外に来たんだい」
もしも井戸に堕ちたのがこの男で無ければ、第七の地平は生まれなかったに違いない。
恨みと憾みを受け入れる、大罪の器としての【イド】。
「もう私は船上にはいない。もうこの嵐は私の命を脅かさない」
分かるかい、メル? とイドルフリートは目を細めた。
荒れ狂う海の上では、幾ら腕利きの船乗りでも余裕など無い。
人間など塵芥のような命。生きることが、生かすことが全て。
その世界をメルヒェンは知らないけれど、想像することくらいは出来る。
「やはり君は少しばかり頭がおかしいようだね、イド」
在りし日の死神の姿をもう一度確かめに来るなんて、普通はしない。
皮肉にも頬を伝う雨粒が、涙のように見えた。
折れそうなほど撓む木々に、まるでこの世界そのものが歪んでしまったかのような錯覚を覚える。
「……君には言われたく無かったな」
森はもう啼いているというより、叫んでいるようにすら聞こえた。
誰の悲鳴を模倣して、そんな唄を奏でているのか。
「おや。それこそ心外だね」
空は宵闇より暗く、冥府より深く澱んでいる。
夜に生きる者でない限り、何も見えないような有様だろう。
いっそ艶やかなほど黒ければ、映す絶望も見えるのに。
「だってこの嵐を引き起こしているのは君じゃないか――メル」
ざぁっ、と雨が一際強くなる。
水に霞む視界の中で、目が合ったことすら気のせいだったかもしれない。
イドルフリートの双眸から、笑みの気配が失くなる。
その代わりのようにメルヒェンは、きゅっと唇を吊り上げた。
「なんだ。知っていたのかい」
「それはこちらの台詞さ。まさかこの地平の構造に、君が気付いていたなんてね」
第七の舞台で、踊るマリオネットは屍人姫。嗤っているのは魔女の幻影。
そして復讐を囁く少女人形、恨みを導く屍揮者、童話を誘う策者。
それを統べる宵闇の名前は、【イド】でも【モリ】でも無いのだと。
真っ白な頁は、即ち鏡。
「最初から分かっていたさ。私こそが此の物語の、自我【エゴ】だろう?」
虚無を虚像に写し取れば、明けない夜へと変わる。
書の記述が蠱惑の花を咲かせた時、存在しないはずの朝が訪れる。
古井戸が変えがたく別つのは、現実と幻想の境界。
月光が堕ちたのは虚構。約束されし恋は虚栄。
こうして【Marchen】は、紡がれ続ける。
「そうさ、謂わば主だ。だから世界は、君に従い続ける」
平然と振る舞っているように見えるのは、上辺だけ。
イドルフリートには分かる。メルヒェンの衝動【イド】、不可分な存在としての彼には。
大罪に呑まれていく記憶。いずれ来る朝への恐怖。誤魔化しきれないその揺らぎが、今まさに吹き荒れ顕現した。
その理由を考えたいとは、思わなかったけれど。
「だったら、話が早い」
闇に紛れる燕尾服。降り止まない雨、耳鳴りのような風。
ひたり、冷たい掌が纏う雫をイドルフリートは感じる。
まるで人間が愛しい者にそうするように、メルヒェンはその首へと腕を回した。
「ねぇ、私の【イド】。この嵐を、止めてくれないかい」
甘えるようにも、縋るようにも、誘うようにも聞こえる声色。
それは無知故の虚言。最後の頁まで辿り着ければ、どうせ全て忘れてしまうのに。
この感傷も、記憶すらも。たった七つの夜を燃やして、シナリオは零へと還る。
策者ひとりを、残して。
また誰かが語るまで、唄が騙るまで、童話は閉じられる。
飽くなき輪廻の、なんと退屈で虚しいことよ。
「……あぁ。私に出来ることならば」
しかしイドルフリートは、抗えない。
彼もまた、地平の【エゴ】に囚われた者。幾度繰り返そうと、逃げ出すことは叶わない。
ただメルヒェンの身体を、確かめるように強く抱きしめ返すだけ。
忘却と喪失の狭間に流れていく、一抹の想い。
雨は未だ、【モリ】を濡らし続ける。
嘘吐きとイデアリズム
(幾つ重ねたら真実へと変わる?)
bkm
←
 →
→

 堕 楽
堕 楽
 嘘吐きとイデアリズム(童話航海士)
嘘吐きとイデアリズム(童話航海士)
 →
→