|
|
ログイン |
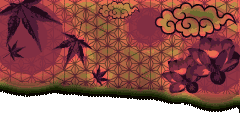

何も見えなかった。
…いや、正確には見えている。
だが、前方も後方も…当然、上や下も見渡せる限り一面が白でしかないのだ。
そう、“モノ”は何も見えない。…もっとも、見たいものなど、今の自分にはなかったが…。
此処が何処なのかは検討も付かないが、現実ではない事は流石に理解できている。
幻想…夢の世界とでも言い表す事ができるだろうか…。
とにかく気が付いたら、自分は此処にいた。
弁慶は膝を抱えたままの態勢で、何もかもを拒絶するかのようにそこに顔を埋めていた。
「…どうしたんですか?」
不意に聞こえた声に弾かれたように顔を上げる。
此処に来てから人の声を聞いたのも姿を見たのも、初めてだった。
気配を全く感じないどころか、声を掛けられるまで、これ程近くに人がいると気付かないなんて…。
普段の自分ならば気を許した相手以外には、ほぼありえない事だ。
…だが、此処では何が起ころうとも驚くだけ無駄なのかもしれない。
何と云っても、現実ではないのだから。
いつの間に現れたのかはやはり解らないが、とりあえずはと声の主を改めて確認した。
ほぼ全身を覆う黒衣を身に纏っており、顔を伺う事はできない。
年の衣は青年と呼ぶ事ができる範囲だろうと、背丈や声色からの大雑把な予想しかできなかった。
しかし、何かが引っ掛かる。
「………」
「どうして、こんな処にいるんですか?」
この違和感を思案し、こちらが何も答えずにいると、黒衣の人物は再び声を掛けてきた。
「傷はもう癒えているのでしょう?」
声色は柔らかいがその鋭い問いは確信を得ており、大きく心が揺さぶられる。
「…っ」その通りだった、もう傷は癒えているのだ。
本来ならば、目覚めて自分の無事をヒノエや敦盛に伝えるのが筋だという事、それは分かっている。
だが、自分が居る事で今回のように迷惑を掛けてしまう事が恐い。
「………敦盛君には傷を負わせてしまいました」
鮮明に浮かぶのは、自分を庇い怪我を負った敦盛の傷…。
「ヒノエの別当としての務めも妨げてしまった…」
それでなくとも、日頃からヒノエには世話を掛けてばかりだ。
僅かにでもそれを返せればと薬師として薬を煎じ、助力をしているが、それが何れ程の足しになっている事か…。
これ以上は、誰にも迷惑など掛けたくなかった。
「僕がいたから…」
そう、自分がいるから余計な災いを招いてしまう。
だから、目覚めたくない…。
「ふぅ…」
弁慶が自分自身を抱き締めるように膝を抱えた時、黒衣の人物が溜め息を吐いた。
「…君はいい子なんですね。迷惑なんて、思い切り掛けてやればいいんですよ」
それは呆れでも嘲りでもない、ただ息を吐いただけのような素直な溜め息だった。
「彼がね…煩いんです。ここ毎日、君が目を覚まさない…どうしたらいい、って …」
静かに待っている事ができないなんて…耐え症がありませんよね…と、楽し気に愚痴を零している姿を、弁慶はぼんやりと見上げるしかできなかった。
「不安に思う事なんてないんですよ…」
そこまで口にした時には、黒衣の人物は音もなく自分に近づいており、眼前にあった。
「っ…、?」
「…大丈夫、君は彼に愛されています」
驚き身を引く前に、自分よりもほんの少し大きな暖かい手の平で両頬を包み込まれ、そっと顔を上げるように促された。
「だから、怖がる事なんて何もありませんよ」
「ぁ…っ」
その顔を見上げた時に、最初に感じた違和感の正体が分かった。
…この人の声は自分に似ているのだ。
いや、声どころの話ではない…今、自分が見上げている顔は…その琥珀の瞳は…、
『弁慶』
不意に宙から落ちて響いた声、…呼ばれたのは…。
「あなたは…っ」
「早速ですね」
続くはずだった言葉は遮られた。
「ほら…彼が“君”を呼んでいますよ」
微笑んだ黒衣の人物は弁慶を開放したと同時に、視界が大きく歪んだ。
そのまま意識も視界も白の世界と共に溶けていくかのような感覚に包まれる。
「嗚呼、そうだ。僕と会った事は…“忘れて下さい”ね」
薄れる意識の向こう側で悪戯っぽさを含んだ声色が、遠くから聞こえたような気がした…。
弁慶がゆっくりと瞼を開けると、隠れていた琥珀の瞳が姿を表す。
「弁慶…」
「……ヒノ、エ…?」
瞳を開けて一番初めに視界を染めたのは緋色の髪とそれと同色の不安気に揺れる瞳だった。
「よかった、…っ!もう、三日もあんたは眠ったままで…っ」
歓喜に満ちた声色で自分を覗き込むヒノエに、罪悪感を揺さぶられてしまう。
「す、すみません、心配を掛けましたね」
三日も眠っていたと聞かされた時は流石に驚いた。
だが、それ程長く深く眠りだったのにも関わらず、視界も意識もはっきりしているのも不思議だった。
「弁慶、何か食べた方がいい」
「……今すぐには…食べたくありません」
勧めに弁慶は眉を寄せた後に緩く首を振ったが、何も口にしないのやはり身体に障る。
「いいから。…ほら、口開けなよ」
「ん……」
ヒノエは半場、無理矢理に用意していた冷やした瓜を口元へと運んで食べさせた。
切り分けてある瓜は丁度、口に収まる大きさで、口に入れた途端に甘味が広がる。
「ぁ…、…甘い…」
口に入れてはくれないかとも思ったが、熟した瓜は甘く甘味好きな彼の口を満足させてくれたらしい。
「…夢を見ていたんです」
「へぇ、どんな?」
二つ目の瓜を呑み込んだ弁慶の言葉に、ヒノエは相槌を打つと三つ目のそれを口元へ運んだ。
「…それが、思い出せないんですよ」
「何だよ、それ?」
瓜を嚥下すると、弁慶は僅かに思案の表情を見せる。
夢の内容を覚えていない事など別段に珍しい事ではない。
普段ならば所詮、夢だと流してしまうのだが、何故か引っ掛かって仕様がない。
しかし、幾ら思い出そうとしても夢の内容は欠片も記憶に残っておらず、府に落ちないながらも思案を止めざるを得なかった。
それに…、
「いいんですよ。それよりも今は、ヒノエと…もっと、一緒にいたいんです」
「…っ」
弁慶の言葉にヒノエは僅かに頬を朱に染める。
目覚めたばかりでは身体に障ってはいけないと、弁慶が目覚めた事はまだ誰にも告げていなかった。
勿論、それは建前で敦盛には悪いが、しばらくは二人きりになりたいというのが本音だったのだが…。
「じゃあ、少し話でもしようか。とりあえずは、食べながら…」
「はい」
四つ、五つ…と、口に入れていけば簡単に瓜は無くなった。
本当ならばもう少し食べて欲しいところだが、あまり無理をさせては逆に身体に障るかもしれない。
ヒノエは空になった器を膳に戻すと、これ以上の食事を勧める事は諦めた。
他には休息以外はする事もなかったのだが、弁慶は眠る事はしたくないと言う。
「なら…弁慶、少し付き合ってくれるかい?」
「ええ…いいですよ」
弁慶へと手を差し述べると、ヒノエは庭へ降りる事ができる渡殿へ連れ出した。
「病み上がりなのに、悪いね」
「庭先ですし、大丈夫ですよ。それに、外の風にも当たりたかったんです…」
ずっと臥せっていた彼には夏の陽射しは強過ぎるかとも思ったが、それは杞憂だったようだ。
「傷…まだ痛むか?」
「いいえ。もう、平気です」
悠々と背を伸ばし息を吸い込でいる弁慶へ問掛けると、いつもと同じ言葉が返される。
様子を見た限りでは言葉通りに思えるが、どうしても疑って掛ってしまう。
「…今度は嘘じゃないよな」
「ふふ…確かめますか?」
「勿論、あんたは嘘吐きだからね」
言葉遊びのように軽口を叩き合ってから、弁慶の身体を引き寄せて、抱き締めた。
少しばかり痩せたようだが、弁慶の笑みを湛えた顔が苦痛に歪む事はなかった。
「…痛む?」
「いいえ」
問掛けに緩く頭を振ってみせたのを確認し、ヒノエは弁慶の細い身体を開放する。
「弁慶…手、貸してくれるかい」
「手、ですか?…どうするんです」
唐突な申し出に首を僅かに傾げながら、両の手を差し出した弁慶の左手を、そっと取る。
「あんたに、“誓い”を贈ろうと思ってね」
ヒノエは小さな何かを懐から取り出すと、それを弁慶の左手…薬指へと贈った。
「ふふ…丁度、いいみたいじゃん」
綺麗に収まったそれにヒノエは満足気に笑むと、そのまま手の甲へと唇を落とす。
「あんたには、金が似合ってる…綺麗だよ」
「…何ですか、これは?」
「“誓い”だよ。さっきも言っただろ」左手の薬指にはめられたのは、幅が小さけ細い金の輪。
「それに…こんな高価な物を…」
「あんたにはこの色が似合ってる、どうしても金がよかったんだ」
装飾は全くないが、とても高価な品である事は安易に見て取れる。
「神子姫様の世界ではね…左手の薬指に合う指輪で、永遠の愛を誓うんだ」
馴染みのない“指輪”という装飾品だが、昔に見た画いて貰ったそれを思い出し、職人に造らせた。
「あんたには劣るけど、綺麗だろ」
「また、そんな事を…でも…ええ、綺麗です」
弁慶は返そうとした言葉を呑み込んだ。自身の指を飾るそれは、本当に綺麗だったのだ。
「本当はもっと玉で飾り立てたかったけど薬作る時とかに邪魔になるだろうから…さ」
「玉なんて、必要りません。…僕を気遣ってくれた…それだけで、いいえ…それが嬉しいです」
そう、欲しいのはヒノエの気持ちだけだ。
何処かの姫君ならともかく、高価な着物や装飾品など自分は要らない。
「それに、これだけでも随分な値になります。その上に玉なんて…無駄遣いです」
「ふふ、想いにそんな価値なんて関係ないよ」
何だかんだと言いながらも弁慶は贈り物を大層気に入ってくれたようで、はにかみながらその金色を眺めている。
「ねぇ、弁慶…オレの全てをあんたにあげる。だからさ、オレのものになりなよ」
「……え?」
耳に落ちたヒノエの言葉に驚いて目線を指輪から彼の顔へと移した。
「僕はとっくに君の…ヒノエのものですよ」
「はぐらかすな。…ちゃんと、意味は分かってるだろ?」
誤魔化すように苦笑しながら述べた言葉は、真剣な顔をしたヒノエには簡単に見破られてしまう。
「それ、は……」
言葉を詰まらせる事は認める事と同意義だが、思わず口籠るのを止められない。
自分達は恋仲でお互いの気持ちは知っている。今更、ヒノエのものになるも何もない。
先程、言葉にした通りに自分はとっくにヒノエのもの…それは本当だ。
だが、それはヒノエの言わんとしている事ではない。
神子の世界では指輪を贈るのは永遠の愛を誓う事だとヒノエは言った。
詰まる処、結婚を申し込まれたと受け取って間違いないだろう。
「オレはあんたが欲しいんだ…」
「ヒノエ…君は熊野別当だという事を忘れていませんか?」
嬉しくないわけなどないが、弁慶は努めて冷たい印象を与えるように言葉を選んだ。
そう、嬉しくないわけなどない。
許されるならば、その申し出を受け入れられたら…どれ程、幸せだろう…。
「君には熊野が……っ僕では駄目なん、です…!」
けれど、それを受け入れるべき人間は自分ではなく、それこそ姫君でなければならない。
気丈に振る舞おうとするが、本心であるヒノエへの想いを抑える度に、声が震えた。
「だからこそだよ」
自分の狼狽振りとは対象的に、ヒノエは冷静で真剣な表情だが、恐怖を感じる事はない。
「…ヒノ、エ…」
「あんたか熊野か…どちらかを択べと言われたら、あんたを選びそうで怖い…」
自分が熊野を捨てる事があってはならないと頭では理解している。
もし、選択を迫られたとしたら自分は、熊野を択ぶ事ができるだろうか…。
けれど、…弁慶がずっと自分の隣にいて微笑んでくれるならば、そんな不安が過ぎる事もない。
「あんたが居るだけで、オレは安堵できるんだ」
「でも…僕は…」
真っ直ぐにこちらを見る緋色の瞳には切なさが漂っており、その瞳から目を逸す事ができなかった。
「だから…、オレのものになって…」
ヒノエの口から紡がれる言の葉は懇願するようなもので、決して強引さを感じさせるものではない。
「ヒ、ノエ……僕は…」
「オレに都合の良い事を言ってるのは分かってる。…でも、オレはあんたが好きなんだ!」
真っ直ぐに自分の瞳を覗き込むヒノエは、いつもの余裕を湛えた笑みではなく、儚気に微笑んでいる。
「答えは…弁慶が決めて?」
「…っ!」
こういう時に限って逃げ道を用意してくれても、嬉しくなどない。
いっそうの事、無理矢理に承諾を求めてくれたなら、断る理由がなくなるのに…。
「……ずるいです」
覚悟をしていたのに…。
ヒノエは熊野の別当だから、いつかは必ず花嫁を迎えいれる事になるだろう。
それまでしか自分はヒノエの傍には居られないが…その時が来たら、大人しくヒノエの傍から消えよう。
そう、覚悟していたのに…。
「ヒノエにそんな事を…言われたら、僕は…断れない…」
覚悟はヒノエの一言で一瞬にして崩れさった。
愛しい人から誓いの品を捧げられて、誓いの言葉を告げて貰えた…、こんな甘美な誘惑を振り払う術など自分は持っていない。
「ずるいです…っ、ヒノエ…!」
堪えていた涙が溢れていくのを、弁慶は止められなかった。
「何とでも。…オレはあんたを手に入れる為なら何でもするからね」
「馬鹿ですよ…ヒノエはっ、!」
悔しさが滲み出たその言葉が嫌悪からくるものでない事は、弁慶の頬を伝う綺麗な涙が物語っている。
「あんたと本当に婚姻を結ぶ事はできないけど…」
こちらの世界の婚姻は形式さえ踏む事ができないから、異世界での誓いしか立てられない。
「あんたを花嫁にはしてやれないけど…」
それでも、二人だけで愛しあえれば…、永遠を誓いあえればいい。
「あんたを想う気持ちだけは本物だからさ…」
腰に腕を回して弁慶の身体を引き寄せ身体が密着させると、唇が触れそうな程に顔を近づける。
「それで…許してくれるかい?」
琥珀の瞳から零れて止まる様子のない大粒の涙を、そっと手で掬い上げた。
「許す…も…許さないも、ありま…せん、…っ」
背徳な関係で許されない関係だと、痛いくらいお互いに理解しているのに、他の姫ではなく自分を選んでくれた。
「僕には、十分です……」
泣きながら笑うという事など無いと思っていたが、本当に感情を揺れ動かされた時にはあるのだな…と、頭の何処かで思った。
「ヒノエ、ありがとう」
「…改めて言わせてくれるかい」
涙を拭う事もせずに自分の胸に顔を埋めた弁慶の耳元に、ヒノエは唇を寄せて囁いた。
「弁慶を一生…愛するよ」
「……僕も、ヒノエだけ…」
赤く染まった頬に口付けた際に自身の唇を濡らした涙を、愛しい気に指で拭い去った。
「愛しい姫君をいつまでも泣かせておくのは、性に合わないんだけどな…」
そう呟いたヒノエの緋色の瞳を奪ったのは、いつの間にか開花した時期外れの紫花…。
「あ、…咲いたんだな」
「……ヒノエ?」
「嗚呼。……何でも、ないんだ」
ヒノエは緩く首を振ると、腕の中の存在に微笑んだ。
庭の隅植えられた紫陽花は、穏やか夏の風にその見事な花を揺らしていた。
終わり。
 : 0
: 0
