|
|
ログイン |
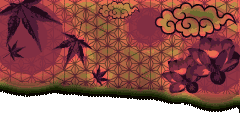

※弁望表現があります。
月光かりーつきあかりーが綺麗な夜だった。
六波羅で八葉として龍神の神子一行が過ごす、京邸に厄介になってから知ったのは、対の存在。
それは自身の叔父であり源氏の軍師である武蔵坊弁慶だと云う。
ヒノエはそれを知った時は何か苦いモノを飲まされたような気がした。
そうして、軍師殿自ら危険を冒し、福原まで偵察に行っていた弁慶が戻ってくるのが今宵だ。
烏の報に寄れば、もうすぐ京邸に姿を現すはずだ。
弁慶が近くに居ると思うだけで心の臓が落ち着かないのだから、自分は重症である。
認めたくなくて足掻いているが、オレは弁慶が好きなのだ。
「まさか、君が出迎えてくれるとは思いませんでしたよ」
弁慶は驚いた顔を作ってみせると、薬やら書物やらを山積みにしている曹司とは別の私室へとヒノエを迎え入れる。
「今、急ぎの書状を書いてしまいますから、待っていて下さい」
話があって待ち構えていたのでしょう、そう言葉を続けて、硯と筆を用意した。
「……ねぇ、何で?」
「っ…」
細い身体を後ろから抱き締める。
蜂蜜色の髪も白い首筋も今は黒い外套の下なのが残念だ。
「ヒノエ……幼子のような悪戯は止めなさい」
綴っていた紙に墨が落ちたらしく、弁慶は大仰に溜め息を吐いた。
「もっと、オレに強請ってよ…」
「何を…?」
「……あんたの為なら、烏くらい貸してやるさ」
自らを危険に晒して欲しくない。弁慶は自分の命を惜しまなさ過ぎる。
福原で幾ら寺社を頼ったとしても、万一にも源氏の軍師と暴かれれば、どうなるかは想像に難くない。
惨たらしく殺されるに違いない。
「あんたがそんな風に死ぬ姿なんて…見たくない」
「……ヒノエ」
細い身体に回した手に力を込めて、言葉を紡ぐ。
「あんたが望むならオレは何でもするよ?」
「では、熊野水軍を源氏に…」
嗚呼、分かっていたさ。
彼はそれしか自分に縋ってくれない。
そして、それは叶えてやる事は出来ないのだ。
「源氏が勝つならね」
「ならば、君に望む事なんてありません。…まして強請るなんて浅ましい真似が出来ましょうか」
貼り付けた人形のような微笑みで、煩いと云うように身を捩る。
「もっとオレに望む事…あるだろう?」
頭を隠していた外套を外して、耳に低く囁く。
灯籠に照らされて茶でも金でもない綺麗な髪が煌めいて…月光かりにも負けていない。
「ふふ、面白い口説き文句ですね。…君にそこまで言われて落ちない姫君はいないでしょう」
どうぞ、神子でも朔殿でも口説いて下さい…そう無責任な事を言い出す始末。
瞬間、頭に血が昇った。
「じゃあ…何で!?」
「ヒノエ?」
途端に怒気を露わにしたヒノエに、弁慶は不思議そうに琥珀を瞬かせた。
「何で……アイツ等には身体を許す!?オレはあんたに取って、あんな雑兵より劣るのか!?」
「何の話をしているんです、ヒノエ?」
「あんたが誰彼構わずに寝てるって聞いたからねっ」
福原から京へと戻っているはずの弁慶は五条にある自身の庵で過ごしている。
それが別に不思議だとか不自然だと思ったわけではない。ただ、好いた相手の行動だから、気になった。
自分が尾行していては、弁慶にはすぐにばれてしまうと、烏に見張らせた。
弁慶は毎夜のように、庵に違う男を招き入れているらしく…。
明らかに節操が無い。
以前から源氏の…九郎の為にならと平家の間者や将とでも寝ている奴だからそうだと思っていたが、近頃、身体を差し出しているのは源氏の雑兵。
そんな利のない相手と自ら望んで寝るなど、弁慶らしくない。
「おやおや、見境がないなんて…僕も軽く見られたものですね」
どんな理由があるというのか…くすくすと笑いを零す弁慶を見遣ると、彼は筆を置くと、こちらを真っ直ぐに見つめてきた。
偽りの色のない琥珀だ。
「皆、僕を愛していると言ってくれたんです」
「……は?」
思わず自分の耳を疑った。
愛してる?誰が…弁慶を?
「信じられますか?鬼子と稚児と蔑まされて疎まれるだけの僕を、愛してると」
大輪の華が咲き誇る…そんな幻覚が見えるような微笑み。
そんな笑み、甥であるオレだって、一度も向けて貰えた事がないのに…。顔も知らぬ相手に嫉妬の念を覚えている自分が惨めだった。
「嬉しくて嬉しくて…」
確かに弁慶は淡い色合いで生まれた所為で、幼い頃から鬼子と蔑まれてきた。
湛快然り九郎然り、弁慶は自分を認めてくれる相手を別段に好く傾向にある事も知っている。
だが、到底納得できる話ではない。
「僕を好きって…たくさん言葉をくれる…」
そんなの、あんたの身体が目的の下衆の嘘に決まってる。
聡いあんたがそんなのに気付かないなんて…ありえない。
「僕には身体しかないでしょう?だから、あげるんです」
「あんたは……っ」
あんたの身体と引き換えに出来る対価なんて、この世にはないのに…。
綺麗で優しくて厳しくて、優雅で気高い…オレの想い人。
「…弁慶、オレじゃ駄目?オレだって、ずっとあんたを愛してる」
「ヒノエ…も?」
先程と同じように不思議そうに瞬いたが、“愛してる”と云う音の効果は絶大だった。
「嬉しい……君が僕を好いてくれていたなんて……」
無邪気に笑い、飛び付いてくる。
本当にこれであの冷酷非情な源氏の軍師なのだろうか…。
そう思う程に、戦場を離れた弁慶の姿に目を疑う。
幼子か子猫のように、ヒノエヒノエと名を連ねて、甘えてじゃれてくる。
それを優しく受け止めてから、緋色の瞳に力を込めて、顔を覗き込む。
「ただし、もうあんたはオレだけのものだ……もうオレ以外の誰にも触れさせない」
弁慶の細い肩が跳ねた。
「……そう、じゃないと…ヒノエは僕を嫌う?」
途端に怯えたように身体を震わせて、瞳を潤ませる。
「嫌…いやっ…嫌わな…で……っ僕は…鬼じゃない、!」
途切れ途切れに紡がれる言葉に、自然と悟る。
嗚呼、これが弁慶の弱味なんだ。忌み嫌われ続けた幼子の成れの果てだ。
「嫌わないよ、オレは…オレだけは絶対に嫌わない」
「…本当に?」
そのまま、弁慶はしゃくりあげた。
その涙は、何の意味を持つのかは分からないが、落ち着くまで、背を撫でてやる。
しばし、涙を零していたが、ようやくに落ち着きを見せる。
「すみません…見苦しいものを見せしましたね」
「見苦しくなんかないさ。やっと本当のあんたが見れたんだ」
ヒノエは優しく微笑んで、弁慶を抱き締めた。
どんなことからも、どんなものにも、奪わせない。そう強くヒノエは思った。
弁慶もそれを受け入れてくれた。
…ヒノエは地上の月を手に入れたのだ。
ヒノエに、愛してるよ…そう囁かれる度に、胸が震えた。
その意味は……、
戦は終わった。
弁慶は五条の片隅で薬師として生きていた。…望美と共に。
ヒノエの恋人であるはずなのに、清らかな神子に惹かれていくのを止められなかった。
そうして、一方的にヒノエに別れを告げた。
久方振りに訪れる熊野の地……父母の墓参りの後、本当は本宮には行きたくなかった。
けれど、望美が本宮に行きたがっているのが伝わって、弁慶も足を運ばざるをえなかった。
見慣れた本宮の邸が視界に入り、近付く度に『愛してる』と囁かれた時と同じざわめき。
落ち着かない落ち着かない。外套に隠れた額に、冷や汗が伝わる。
「突然ごめんね、ヒノエくん。弁慶が内緒にしちゃったから…」
「やぁ、望美。お前なら何時来たって歓迎するさ。オレの姫君」
オレはまだ諦めてないよ…などと甘く囁くが、望美は笑って受け流すだけだった。
「あ、湛快さんとヒノエくんのお母さんにも挨拶してくるね」
元気のよい望美は、勝手知ったる本宮の渡殿を駆けて行った。
それを弁慶は複雑な表情で見送る。
ヒノエと二人きりになってしまった焦燥感ばかりが迫り、小さく拳を握り締めた。
「弁慶も…よく来たね」
よくオレの前に来れたね…そう威圧的な緋色がこちらを射抜く。
僕はヒノエに会うのが恐かったのだ。
「………お邪魔しますね」
確かに、ヒノエと弁慶は恋仲だった。
別れたいと告げても弁慶を深く愛していたヒノエは、承諾をしてくれなかった。
ヒノエは確かに優しかった。何の文句のない完璧な恋人だった。
しかし、優しくされればされる程に、弁慶は気付いたのだ。
自分はヒノエを愛せていないのだと。
「弁慶…今宵、待ってるよ」
勝手に外套を外し、愛おし気に蜂蜜色の髪を指に絡めたり、手で梳いたりを繰り返す。
「……行きません」
「へぇ、来なかったら?」
先程まで髪を愛でていたとは思えない程乱暴に強引に髪を鷲掴まれ、顔を覗き込まれた。
唇が触れそうに近い。
ヒノエの整った面立ちが眼前にあり、逃れようと身を捩るが腰にはすでに腕を回されて、捕らえられていた。
「いい加減、退屈な暮らしにも飽きてきたんじゃない?そろそろ、新たな戦の火種があってもいいんじゃないか……ねぇ、弁慶そう思わない?」
「…っヒノエ」
ぞくりと背筋が凍る。
それは初めから、拒む事の出来ない誘いだったのだ。
「ヒノエ……もう、これで最後にして下さい…」
「嫌だよ。言っただろ?“もうあんたはオレだけのものだ……もうオレ以外の誰にも触れさせない”って」
別当の執務を行う曹司に放り込まれて、後ろ手に拘束された。
床から懸命にヒノエを見上げて懇願する。
確かにヒノエには感謝している。ヒノエがいなければ、ヒノエに愛して貰わなければ、自分は未だに“愛”に飢えて馬鹿な真似を繰り返していただろうから。
だが、自分の意思ではどうにもならないのが懸想の心だ。
ヒノエだって、弁慶への想いを持て余して、こんな凶行に及んでいるのだろう。
「僕は父母の墓に誓ったんです…」
彼女と一緒に生きていこうと…。
「彼女と過ごして、僕は初めて愛を知ったんです…だから、ヒノエ」
「関係ない」
冷たいヒノエの声に涙腺が緩み、視界が滲む。
腕と背は床、はしたなく足を開かせ、その隙間に身体を滑り込ませた。
怯えているのか抵抗しているのか、震えている弁慶の身体を力で押さえ付けた。
「…ぁっ、やめ…!」
「綺麗だよ、弁慶……」
抗えない弁慶を余所に、着物を脱がし乱していけば、夜目にも白い裸体が露わになる。
腕の拘束の為に着物を完全には脱がせていないが、この際それは構わない。
「…僕を少しでも愛してくれているのなら……お願い」
「関係ない…関係ないよ、弁慶。もう、あんたが誰を愛していようが関係ない」
弁慶が幸せならオレも幸せだよ…そう言ってやる事など出来なかった。
首筋に強く噛み付く。
「あぅっ…!」
小さな悲鳴が耳に心地よいと、痕を残し舐めあげる。
「あんたはオレのものだよ、弁慶」
「っぁ…あ!」
香油を閉じた蕾へ垂らせば、その感触にあがった弁慶の声に、ヒノエは口の端をあげて笑った。
そのまま指を押し挿れて掻き回し、香油を内壁へ塗り込んでいく。
探り慣れた前立腺を強く刺激し、奥へ奥へと誘うように締め付ける内を指で掻いてやる。
「う……ぁっ、あ…!」
快楽に慣れた身体は、前には触れずとも後ろへの刺激だけで、彼自身は主張を始める。
「ほら……もう感じてる。あんたはオトコ無しじゃあ生きていけないんだろう」
「やっ…違…って、!」
弁慶の心を抉るように、残酷な言葉を吐いて、付け入って…逃れられないように。
否定の言葉はこれ以上は聞きたくなくて、内に挿れた指の本数を増やし、それぞれに動かした。
「平気でどんなオトコにも身体許してた癖に…」
「あ…っそれ、は……」
それを言われてしまえば、弁慶は何も言い返せない。
ほら、やはり口を噤んだままに、目線を逸らした。
触れて欲しいと赤く実った胸の飾りも摘んで、指の腹で転がす。
胸の飾りを弄られるのが弱いらしく、反応が更に敏感になる。
見る見るうちに、彼自身は先走りの蜜を零していくが、流石に後ろだけでは達けないようで、苦し気に震えている。
このままでは苦しいだろうと、真っ赤に腫れたそれを激しく扱きの先端に爪を立て促し、一度達かせてやった。
「ひっあ、ぁああっ」
一際かん高い嬌声を上げて、呆気なく蜜を吐き出した。
「……ん、んん…はあ、は、ぁ」
荒い呼吸を繰り返す唇を奪い、強引に舌を絡め取る。
深い接吻に弁慶は入り混じった唾液を呑み込む事が出来ずに、顎を汚した。
「はっ…ぁ……っのえ」
「………弁慶、可愛いね…もっと、淫らな姿を見せてよ」
萎えた弁慶自身に触れる。
蜜を吐き出して敏感になった欲望を銜えて、舌を絡めていく。
「ひ……っだ、め…っああ、!」
独特の苦味が口腔に広がったが、弁慶の蜜だと思えば甘露にさえ思える。
溢れるそれを丁寧に舐めて吸って、飲み下す。
時折、歯を立てて、口から離し熱い息を吹き掛けた。
「…んあっ」
「ふふふ、これ…望美に挿れてやってるの?」
「っ!」
恥辱を煽る言葉に、情事に蒸気していた頬が耳まで真っ赤に染まった。
相も変わらず、言葉で嬲られるのが好きらしいと、ヒノエは意地悪く笑む。
「あんたは薙刃振るってるより、オンナを犯してるより……オトコを銜えてる方が似合ってるぜ」
「ぁう、ヒノェ…っ」
あまりの羞恥に弁慶は琥珀から涙を零す。
「嗚呼、泣くなよ。オレはあんたに泣かれるのには弱いんだから…」
困ったように笑い、眉根を寄せたヒノエはその涙を自身の着物の袖で拭ってやる。
優し気な仕草に弁慶は知らず知らずの内に微笑んだ。
だが、それは間違いだとすぐ気付く。
「…もっと鳴かせれば、泣く余裕もなくなるよな」
「ぇ……何を…痛っ」
力の抜けた身体を簡単に返されて、双丘を相手に突き出す形になる。
香油と蜜に濡れた蕾から、それらが滴り落ちて、実に妖艶な姿だ。
「……気持ち悦くなろうね?」
弁慶のあられもない姿に反応していたヒノエは、己の欲望で貫いた。
「んっ、ぁああっ…!」
「く…っ」
「や、ゃあっ…抜い……やあ、!」
圧迫感のある異物…欲望をきつく締め付けてくる内に、ヒノエは息を呑んだ。
「締め付け過ぎて、抜けない」
そのまま猛ったそれで掻き回して、前立腺を擦れば、嬌声を抑えられないようだ。
後ろから責めている為に弁慶の顔は見えないが、きっと汗や涙、唾液に厭らしく濡れた淫らな顔をしているに違いない。
勝手に楽にならないようにと根元を戒め、激しく突き上げる。
「ふあっや、ぁあっあ!!」
「ほら、腰が揺れてるよ?気持ち悦いんだろ?」
きつくきつく根元を戒めた弁慶自身に思い切り爪を立ててやれば、急激に内は狭くなる。
「うぁっあ!も…無理…っ!」
「しばらく抱いてない内に、随分と甘えん坊になったねぇ…以前なら、これくらい耐えられてただろ?」
激しく弁慶自身を扱いてやれば、掠れた悲鳴があがった。
「…ぁああっあ!」
「すごいねぇ…あんたは縛ったままでも達けるのかい?」
「もぅ……、や…むりぃ…」
途切れ途切れの縋る言葉…ヒノエは一気に身体が熱くなるのを感じた。
「仕方ない、ねぇ…っ」
質量を増したヒノエ自身を更に締め付けた内に、白濁の欲望を吐き出し、弁慶自身への戒めも解いてやった。
「ひあっふ、あ、あぁっ!」
我慢させていた所為か二度目の吐精も、随分と濃かった。
「相変わらず淫らな身体だね。悦かったよ、弁慶」
「………あ」
ゆっくりと欲望を引き抜けば、蕾から白濁と香油が混じったそれが床を汚す。
その床に倒れ込んだ弁慶の床に広がる髪が、白い肌が濡れて汚れる。
「あ…は、……ぁ、う……んん…」
「弁慶、泣かないでよ」
腕の戒めはそのままだ。拭えない止まる事のない涙を掬ったは、ヒノエの熱い舌だった。
「別に此処に監禁するつもりはないさ。たまに熊野まで会いに来てくれればいい」
オレが京くんだりまで会いに行ってもいいけれど、それじゃあ望美に気付かれてしまうだろう?
「アイツは妙に鋭いからね」
月光かりを浴びながら、乱れた着物を直すヒノエの唇は実に妖艶に笑っている。
だが、緋色の瞳は少しも笑っていなかった。
緋色の少しばかり癖のある髪を掻き上げて、弁慶の耳に低く甘く囁く。
「どんなことからも、どんなものにも、奪わせない」
弁慶の耳に牢の格子が閉まる…そんな幻聴が聞こえた。
終わり。
 : 0
: 0
