|
|
ログイン |
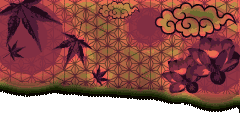

妖が目撃されるという刻限は日がくれて夜の帳が降りた頃だ。
敦盛はその刻を見計らい、ヒノエに見送られ邸を後にした。
ヒノエは後から敦盛に合流する手筈になっている。
地に足を着けずに宙を滑り、都の路を漂う。
式神には歩くという行為よりもこちらの方が余程、楽に動けるのだ。
徒人には見えぬように計らっている為、妖だと騒ぎ立てられる心配もなかった。
仮に陰陽師に遭遇しても、自分が式神である事は安易に分かる事であるから、危険はない。
夜風に流した濃紫の髪と、薄衣が揺れていた。
路に人間の人影はない。
これでは、噂の妖と遭遇するのも手間かもしれないと、僅かに眉を寄せたその時、…何処からか唄が聞こえてきた。
悲しい声色で静かに唄うのは男にしては僅かに高い色のある声。
聞く者を悲しみの淵へと誘うような深い歌だった。
「来たか…」
それがすぐに人間のものではないと察した敦盛は、その場で足を止めた。
敦盛の声に気付いたようで、何もなかった宙から人影が現れる。
薄衣でできた被衣を身に付けた狐の妖は、獣の耳と尾は隠せていなかったがほぼ完璧に人の姿を模していた。
噂の通りに美しい姿であり、蜂蜜色の毛色は狐のものだとしても不思議な色合いだった。
「…誰…ですか?…邪魔をしないで」
人の言葉に慣れていないのだろう妖の言葉が、何処か舌足らずであり非常に聞き取り難い。
「何故、人々を騒ぎに巻き込んでいる?」
「…妖はただ一度しか名を告げる事ができない。……もう告げてしまった」
問いを投げ掛けると、こちらに敵意がないのを分かってくれたようで簡単に答えが返ってきた。
知らない者が聞けば、的を得ていない答えだと思うかもしれないが、敦盛はすぐには理解する。
今、狐の妖が口にした通りに、妖は長い生涯の中でただの一度しか自身の名を告げる事ができないのだ。
妖にとって名は弱味にしかならない為に、告げる相手は当の妖が決める。
「貴方はもう…?」
「小さな人間の幼子だった。…その人を探しているだけ…」
本来ならば同じ妖相手に名を告げ生涯が共に過ごすのが常だが、この狐の妖は人間に告げたのだ。
妖は一度、相手を想えばその想いを変える事はない。
しかし、人間の心や想いは妖とは異なり、時の流れの中でとても移ろい易いものだ。
「相手が覚えていなかったら、どうするのだ?」
「それでも、もう…告げてしまった」
その可能性が強い。
増して、相手は幼子だったと云う…子の想いは純粋なものだが、記憶があるか否かは希望が薄い。
「どんな姿か分かってはいるのか…?」
敦盛の言葉に、表現のなかった妖のその顔が一瞬にして深い哀しみに染まる。
「…人間と妖は、生きる刻が…違う…あれから幾年の年月が経ったのか分からない…」
悲し気な声色にこちらにまで哀しみが伝わってくる。
「嗚呼、あの子は今どんな姿をしているんでしょう…」
もう、刻限が迫っている…そう狐の妖は呟くと、獣の耳を反応させ動かした。
妖が地を僅かに蹴り上げると、その身体が宙に浮かび蜂蜜の毛色が夜風になびく。
「…早く会いたい。……そして、僕の名を…」
小さく呟いた妖は夜の闇に溶けていくかのように姿が消えていく…。
「待て!」
敦盛が妖を呼び止めた時、何処からか符が飛び、妖の身体に張り付く。
次いで、敦盛の耳に聞き慣れた声がした。
「…少しは大人しくして貰えるかな?」
「ヒノエ…!」
放たれた符とヒノエの声に、目線を向けた敦盛の濃紫にヒノエの姿が映った。
僅かに安堵の表情を見せる敦盛の傍らへ駆け寄ると、ヒノエは妖に対峙する為に符を構える。
「…ぅっ!」
符は痛みを伴うのか僅かに眉を寄せた狐の妖は、消えるのを諦めたらしく地に膝を付く。
ヒノエはその隙を逃さずに、何言かを呟くと印を結び、妖をその場に動けぬように縫い止めた。
「これ以上、好き勝手にさせたら…面倒が起こるんだ」
「ぁ……」
足を固定された妖は表情を変えないままに、伏せていた顔を弱々しく上げる。
そして、ヒノエの顔を覗き込んだ途端にその無表情が一変し、微笑みを浮かべた。
「あ…っ、…みつ、けた」
感極まったような明るい声色。
感情のまま簡単にヒノエの術を振り払い、身体を地から浮かせた。
「何…っ!?」
「ヒノエ、っ!」
「みつけた、…見付けた、見付けた…!」
術を解かれたヒノエが応戦する間を与えず、重みなどないかのように身軽に宙を舞う妖は、音もなくヒノエに近寄る。
「この…っ、!?」
「君が助けた…君と“約束”した…君は言った…」
嬉しい想いが溢れ出て、巧く人の言葉にならない。
“オレが大きくなったら、あんたを守ってあげる。あんたとずっといっしょにいてあげるから…”
“なっ、約束だよ”
緋色の髪と瞳を持つ幼子、その時の言葉と微笑みを昨日の事のように思い出す事ができる。
満面の笑みを浮かべた妖は、幼子の頃の面差しを残したままに成長したヒノエをまじまじと見つめる。
「“約束”した…会いたかった…」
あの時からほんの少しも変わっていない想いを全て込めて、口から人の言葉として落とし、ヒノエに手を伸ばした。
「……っ、!」
その鋭利な爪が自分へと伸び、ヒノエは印を結ぶ事もできずに身構える。
狐は危険だ…そういつもなら身体が…頭が警告を出すはずなのに、今回は勝手が違った。
冷静な判断が下せない。
その為に、妖の指先…正確には鋭利な爪先が頬に微かに触れた。
「っう…、!」途端に頭に何かの光景が蘇る。
自分の記憶であるはずなのに幼い自分の姿まで映っている…その言葉には言い表せない奇妙な感覚が、感情を掻き回す。
「…っ触るな!!」
「…?」
ヒノエに伸ばした腕を大きく振り払われ、妖は一度大きく瞳を瞬かせる。
次いで、小首を傾げた…ヒノエの行動が理解ができないというように。
「……?」
「オレは…あんたなんか知らない、!」
その妖の仕草に苛立ってヒノエは声を荒げた。
「ヒノエ、その妖は君を傷付けようとしたのではないんだ!…ただ…っ」
「煩いっ、!」
口を挟んだ敦盛にさえ耳を貸さずに、ヒノエは幾度が頭を振った。
妖はヒノエの様子に先程まで浮かべていた満足の笑みを消すと、不安の色を見せる。
「ずっと…待っていた…会えるの、を…」
「知らないって言ってるだろ!妖なんか知らない!」
ヒノエから受けた二度目の拒絶に息を飲む。
「ぁ……」
先程、濃紫の式神に言われた事を思い出す。
“相手が覚えていなかったら、どうするのだ?”
そう言われたのだ。
「…君も…………所詮は人間…」
改めて思い知らされた。
妖とは異なり、人間の心や想いはとても移ろい易いという事を…。
あの優しかった幼子が今では自分を拒絶するだけなのだ。
喜びの代わりに哀しみが溢れて心を支配すると、琥珀の瞳が涙に揺れ獣の耳が僅かに垂れた。
「でも、名を呼んで?言って?もう会わないから…最期に僕の名を…」
本当にこれが最期のつもりだった。
だから、最期に一度だけでも自分の名を読んで欲しかった。…名を告げた、ただ一人の相手に…。
「お願い……しま、す…」
「知らないんだよ!」
それさえも拒まれて、鋭い緋色の瞳で射抜かれた。
また、身体から力が抜けていく…ヒノエから拒絶を受ける度に、確実に力を失っている。
「………っ」
何か熱い液体が瞳から溢れ、頬を伝った。
「…妖は、約束を違えない。……早く来たから、罰……?」
それを拭う事などせずに、妖は夜の闇に溶けて消えていった。
哀しみに満ちた言の葉の呟きを残して…。
邸に戻ったヒノエは、冬の夜風に晒され冷えた身体に火鉢で暖を取る。
「……後味悪過ぎ。…結局、何の解決になってないしね」
珍しく苛立っているヒノエは不機嫌な事を隠そうともせずに、眉を寄せていた。
「……ヒノエ」
「っ…、敦盛も来るかい?」
敦盛に不安気に名を呼ばれれば、ヒノエはばつの悪そうな顔をすると、彼を自身の傍らに置いた火鉢へと手招きする。
勿論、式神である敦盛には暑さも寒さも関係ない為に、それは形ばかりのものだ。
しかし、それは敦盛をわざと常の式神と異なるように作ったヒノエのこだわりだった。
「あぁ」
敦盛もその気遣いに甘える事は嫌ではなく、素直に招かれた箇所へ膝を折る。
「……ヒノエ…何故、妖が一度しか名を告げられないのかを…知っているか?」
「名が弱味になるからだろ」
正に不快の根源である妖という言葉に、ヒノエは目線を合わす事もせずに愛想なく答えた。
「そうだ。告げた名が…名を告げた、ただ一人の相手が弱味になる」
敦盛は一つ頷くと言葉を続ける。
ヒノエは聞きたくなどないのだろうが、どうしてもヒノエには聞いて貰わなければならないのだ。
「その者を傷付けられる事も苦痛であり弱味になるのは勿論だが、弱味の意はそれだけではないんだ」
「…ぇ、?」
そこでようやく、興味を持ったらしいヒノエは、困惑した顔を敦盛へと向けた。
敦盛の言葉は初めて聞くもので理解ができない。
ヒノエの勘の良さが、何かを自分の中で警告していた。
「敦盛…それ、どういう…っ?」
「妖は名を告げた相手に名を呼んでもらえなければ、徐々に力が失われていくんだ…」
敦盛は淡々と答えていたが一旦言葉を止めると、言い難そうに付け足した。
「名を告げた者に、一度でも拒絶されれば…力が消えてしまう」
「な…っ」
言葉を失ってしまう。
妖が力を失うという事は、人間で言えば“死”…それと同意義なのだ。
人間から言わせれば奇妙なものに思えるだろうが、妖は一度想えば一途で、心を変える事などない。
本来ならば名は妖同士で告げるべきものである為に、問題など起きないのだ。
「…妖は名を告げた相手を間違えるわけがないんだ。名を告げる事は命を差し出すのと同意義なのだから…」
驚いたままのヒノエを見遣った敦盛は、至極真剣な表情で告げる。
「ヒノエ…君は覚えていないのかもしれない。…だが、あの妖にとっては君と交した“約束”が全てだったんだ」
妖はずっと捜していたのだろう。名も姿も分からない、幼子の頃しか知らない相手を。
そして、ようやく見付けた。
ヒノエに会う前は淡々とし表情などなかったのが、途端に一変した妖の様子を見れば明らかだ。
「それだけは分かってやって欲しい…」
「…そんな事言ったって……オレは…っ」
否定の言葉を言い掛けて…ふと、頭に浮かんだ光景がある。
それは先程、妖に触れられた時に蘇ったものと同じだった。
幼い自分は傷付いた珍しい毛色…蜂蜜色の狐を助けて、必死に看病したのだ。
父親が陰陽師である事が関係しているのか、狐が妖だとはすぐに気付いたが気には全くならなかった。
狐の傷も治り掛けた頃、その狐と“約束”した。
別れ際に、綺麗な優しい声が頭に直接聞こえて…。
“僕の名前です…忘れないで、君が大きくなったら、会いに行きますから”
“約束します…”
そして、見る見る内に遠ざかる狐の姿に自分は叫んだ。
『絶対、忘れないからっ!』
そうだ自分の身体はあの別れ以来、狐の妖を拒絶するになったのだ。
………思い、出した。
「あの妖が…あの時の狐?…名前をオレに教えた…?」
あの狐の妖は自分に名を告げたと言った…そして、自分は相手を拒絶してしまった。
それは、つまり…。
「敦盛……あの妖は今頃…、っ?」
恐る恐る問い掛けたが、答えなど決まっている。
「嗚呼、無事ではないだ…っあ、ヒノエ!?」
敦盛の言葉を最後まで聞かず、ヒノエは邸を飛び出す。
妖のいる場所になど宛てもなかったし、会えたとしてもどうするかなど分からない。
だが、どうしても居ても立ってもいられなかった。
だって、自分は“約束”をしたのだ。
 : 0
: 0
