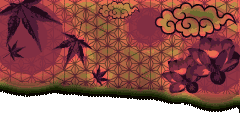

涙の訳を教えてくださいー1ー
※つらい恋5題『1 どうしても止められなかった』と君の手を引く5題『4 ごめん それでも』からの続き物です。
※ヒノ弁に子供がいます。さらに、弁慶が育児ノイローゼ(?)気味です。
平家との戦は終結していたが、九郎は快く源氏に…軍師の地位へと迎え入れてくれた。
偶然とは云え見計らったように戦が激しさを増した途端に消えて、終結した頃に現れた自分を戦から逃げたと陰口を叩く者も多かった。
当然の事であると甘んじて受けていたが、九郎はそんな中傷からも庇い、ついには兵を説得し治めてくれたのだ。
偽りだらけの咎人にさえ、こんなにも優しい九郎を守らなければならない。
その覚悟は迫り来る源氏の…鎌倉の軍勢を前にしても変わらない。
合戦の最中から九郎を驚異に考えた鎌倉が、彼の始末を望んでいたのを知っていた。
だからこそ、自分は源氏に戻ってきたのだ。
以前から平泉へと文を烏に届けさせていた甲斐もあり、藤原秀衡は逃れてきた九郎や己を幼少の頃と変わらずに庇護してくれた。
だが、圧倒的な兵力の前に平泉が陥落するのも刻の問題である。
「さて…何処で待ち伏せたものかな」
策があると言いくるめて早々に九郎には逃げて貰ったが、兵の足止めも必要である。
少しでも彼が遠くへ逃れる為ならば、後から追うと交した約束を違える事もいとわない。
「くっぅ…あ、!」
幾多の矢が腕に足に身体へと突き刺さるが、引くわけにはいかいと唇を強く噛んだ。
痛みに悶える隙にと兵が勢い付くが、近寄った手前の兵から順に首が落ちていく。
弁慶が鋭く薙刃を振るう度に、溢れ出た鮮血が宙を舞った。
約束の通りに自分を信じて振り返らずにいてくれる九郎の為にも、今はまだ死ぬわけにはいかない。
「倒さないと…っ」
せめて…あと一払い、あと一薙ぎ。
「倒さないと倒さないと…守らないと……っ、!」
九郎と自分は唯一無二の親友で、絶対の親愛で結ばれた間柄だと信じている。
そんな九郎と交した約束を初めて破った償いにと、ただひらすらに薙刃を振るった。
「っう…わぁああ!」
多量の鮮血が飛び散り、数えるのも馬鹿らしい程の幾度目かの断末魔が響く。
どれだけの間、薙刃を振り続けていたのかは知る事ができないが、ようやく敵も僅かに引いたのだけは分かった。
「………っ、!」
見渡す限り動く者は己以外はない。
穢れのない六花だけが深々と降り積もり、戦場に似つかしくない不気味な静寂が訪れる。
「……こんなに、無茶をしたのは…九郎と京で暴れ回った頃以来、かな、?」
薙刃を地に突き立て、辺り一面に転がる骸を踏み付けながら、必死に崩れ落ちそうな身体を支えた。
「はぁはぁ…っ、」
荒い呼吸を繰り返し息を整え、腕や足に突き刺さる弓矢を引き抜いていく。
「…うっ、ぁ」
幸いにも心臓を貫いた矢はなく、激痛にうめく程度で済んだようだ。
だが、痛みを感じたのは初めの数本だけで、すぐに感覚は麻痺し痛みさえ感じなくなる。
ぼんやりと呆けた途端、背後に人の気配を感じ取った肌が粟立つ。
「―っ…!?」
背後の気配に気付かぬ程に油断していたわけもなく、認識するよりも早く反射だけで薙刃を振りかざした。
勢いよく刃が打ち合う音が響く。
「…っく、!」
傷だらけの身体をずっと雪と寒さに晒していたのだ、体力の衰えも相まって薙刃を握る力が弱い。
必死に震える指が限界を訴え、血に濡れた指先が滑る。
…呆気なく薙刃は弾かれて、地に落ちた。
「随分、弱くなったね…オッサン」
「………ヒ、ノエ?」
ヒノエがわざとその呼称で呼び嘲笑うような声を掛ければ、弁慶はそこでようやく相手がヒノエだったと認識したようだ。
本来ならば平泉になど居るはずがないヒノエの姿に、弁慶は酷く驚いた顔のまま幾度か瞬いた。
だが、弁慶が驚愕したのは一瞬で、すぐに琥珀の瞳には鋭い眼光が宿る。
「邪魔をしない、で下さ…っ倒さないと…僕は九郎を守るんです…倒さないと… !」
「もう、いないよ……もう、敵はいない」
まるで壊れたからくり人形のように、それを繰り返す弁慶の両の肩を強く掴む。
先程、弁慶の背後から得物を弾き飛ばしたのは正しい判断だった。
こんなにも殺気立つ弁慶の眼前に立てば、有無を言わさずに斬り殺されてしまいそうだ。
「残ってたのは熊野の水軍が倒した」
流石に熊野として横遣りを入れるわけにはいかないので、平泉の兵を装って加勢したのだが…。
まぁ、そんな事は弁慶にとっては意味のない話だ。
「殆どはあんたが倒した後だったけどな。…まさに鬼気迫る荒法師ってところか」
「……ほんとう、に…?本当に…もう、鎌倉の兵はいないんですか?」
まだ、状況が理解できないらしく戸惑っている弁慶の瞳は、“九郎はもう大丈夫なのか?”そう訴えていた。
それを察していたヒノエは、心得た様子で弁慶にゆっくりと頷いてみせる。
すると、脅えたようにヒノエの着物を握り締めていた弁慶の手から力が抜けた。
「……ょ…った、…よかった」
これで、九郎は鎌倉の追手など届かない地まで逃れる事ができるだろう。
安堵と共に張りつめていた糸が切れたようで、倒れ込む弁慶の身体をヒノエはしっかりと支えた。
「九郎はもう大丈夫だ。…だから、次はあんたの番だぜ」
次いで、弁慶の頬にまで及んでいた誰のものとも分からない血を拭い去った。
「……帰ってきなよ、熊野にさ」
「熊野になんて、御免ですよ…僕はもう此処で先に逝って、九郎が来てくれるのを待つんですから」
そのやけに優し気な手を弁慶は、鬱陶しいと言わんばかりに払い退ける。
「九郎にもう会えないのは分かってるみたいじゃん。…なら何処に居たって同じだろ。熊野には、あんたを必要としてる奴がいるんだぜ」
そう前置きしたヒノエは、何故自分が平泉まで遠路遙々下って来たのかを簡潔に説明してみせた。
「赤子ってのは不思議でさ…あんまりに母恋しいって鳴くんだよ」
乳母に云わせれば他の赤子に比べて夜泣きも酷くない―もっとも、ヒノエからすれば随分なものに思えたが―緋鶸は、ヒノエが母の事を話した時だけは火がついたように泣き喚くのだ。
「律義にあんたの事には一切関わってなかったけど……あんたが死に掛けてるのに、放っておけないじゃん」
源氏の動向は知ってはいたが、関わらぬようにと自身を戒めていた。
結局は、赤子に後押しされる形になってしまったのだ。きっと、母のそれを必死に伝えようとしていたに違いない。
「緋鶸が待ってるよ」
「…ふざ、けないで…下さっ、!」
子の名を出した途端に、弁慶は狼狽した。
寒さの所為ではなく粟立つ肌を擦ると、嫌悪するようにヒノエに一睨みくれてやる。
「嫌です、よ!…僕に関わらないと約束したでしょう!…だいたい、今更…っ母親になんてなれないっ」
「ゆっくりでいいんだよ」
弱々しくも悪態を吐く弁慶が、それでもヒノエから離れないのは身体が動かないから。
それを知っていてヒノエは弁慶を逃がすまいと、その背に腕を回した。
「ゆっくりでいい、だから…母親になって欲しいんだ。オレの事は今更どうでもいいだろうけど、約束に緋鶸の事は含んでなかったじゃん」
己は弁慶に関わらないと約束したが子の事までは誓っていないと、ヒノエはらしくなく幼子のような屁理屈を並べた。
「僕は咎人です、…母親になんて、なる資格なんかないんですよ」
「咎人なのは“弁慶”だ。…あのいけ好かない真っ黒軍師のオッサンは、今日死んだの」
拒絶の色を濃くする弁慶の蜂蜜色を乱暴に掴むと、カタールで一気に斬り落とした。
はらはらと、絹のような髪が舞い散る姿は戦場には似つかわしくない程に綺麗だ。
「ちょ…っ、!」
「……分かる?…あんたは今から、そうだな…何て名前がいい?」
本当の名は嫌なんだろ…などと強引に話を進めるヒノエに、弁慶は髪を切っただけで“弁慶”は、死んだ事になるのかと云う言葉を挟む間もない。
「……“僕”はもう、死んだんです…ヒノエに任せますよ」
「じゃあ、そうだな……」
もう抵抗するのも億劫だと、弁慶はようやくにヒノエに身体を委ねた。
「帰ろうか、弁慶」
そんな彼女をその名で呼ぶ。
一寸意外そうそうな顔をした弁慶に、“弁慶”であったあんたを否定なんてできないだろと、笑ってやる。
「………」
「疲れた?…ゆっくり休みなよ」
それには否定も肯定さえもせずに、弁慶は疲れたらしく何もかも諦めたような虚ろな琥珀の瞳を、ゆっくりと閉じた。
弁慶の華奢な身体は傷だらけでまずは何よりも手当てだと、障らぬように抱き締めた。
ヒノエに似た顔立ちと緋色の瞳、弁慶に緩やかな似た蜂蜜色の髪を持つ幼子。
名は緋鶸と云い、歳の頃はまだ三つか四つ程の子だ。
身の丈は並だが、身体は脆く時折、激しく咳込んでいる。
身体が弱いにも関わらず、大きな病を患っていないのは邸に閉じ込めているからで、何時かかってもおかしくないと薬師から宣告されている。
それでも小さな病は絶える事がなく、血の繋がりを口外しない口の堅い薬師に診させていた。
自分と弁慶の…甥と叔母の子だから、血が濃すぎるのが虚弱の原因なのだから。
ただでさえ、出生を隠さなければならないのに緋鶸は男児。
それが知れれば、次期別当のいさかいに巻き込んでしまうかもしれないと、人気のない界隈の邸に弁慶と共に住まわせていた。
賑やかな界隈から離れた一際緑の美しいその環境も、弁慶や幼子には好ましいものである。
初めの心は戸惑い馴染めずに、嫌悪さえ漏らしていた弁慶も月日が経つに連れて、少しずつだが気を許してくれていた。
ヒノエは足繁く通いー当然、別当としての役目を放棄はせずにー弁慶の心を溶かして、己に向けさせた。
その努力もあり、弁慶を平泉から熊野へと連れて来て二年も過ぎた頃からは、弁慶も母親として緋鶸に接している。
色々と目下の悩みなどはあったが、それなりに平和な日々だったのだ。
音もなく雪が降り注ぎ一際冷えた空気が着物を通り過ぎ、寒さが身に凍みる冬のある日…ー
ヒノエは自分の家族の暮らす邸への路を急いでいた。
それまでは頻繁に邸へと訪れていたが、別当の遠出や執務が重なり三月も文で報さえも取れなったのだ。
久方振りに訪れた邸、一番に聞こえてきたのは“おさえりなさい”との常套句ではなく、幼子の泣きじゃくる声。
「ひっく…っふ、え…、ひく、!」
「…緋鶸、?」
ヒノエは訝し気に子の名を呼んで、己と弁慶に似た風貌の姿を探した。
広くはない邸である。程なくして邸の端に蹲った緋鶸を見つける事ができた。
だが、緋鶸を緋色の瞳に映した途端にヒノエは表情が凍りつく。
「……ひわ…っ!?」
「ふぇ…てて、さま?…っててさまぁ…!」
頬は真っ赤に腫れて、着物の隙間から見えた腕や足には痣があり青く変色している。
「ふぇ、うゎ…っ、あぁあん…!」
「大丈夫だ、緋鶸…もう痛くないよ、ほら…!」
痛々しい子の姿に驚愕しながらも、必死に泣き止むようにあやした。
常ならば呆けており何処か冷めた雰囲気を持つ子が、これ程に泣きじゃくっているのは尋常ではない。
「どうしたんだ、緋鶸。…大丈夫だから、オレに話してみな」
「…ん、かかさまが…っ、ぶつの」
ようやく泣き止んだ幼子に事情を伺えば、戸惑いながらも懸命に言葉にしていく。
「ててさまとおんなじめ、で…みるな…って…」
「ぇ…かかさまって…まさか、弁慶が?弁慶が叩いたのか、緋鶸っ?」
頬の腫れはまだ真新しくつい先程のものと分かる。真っ赤な頬も青く変色した痣も見る限り、一度二度躾に叩いた程度のものではない。
ヒノエは慌てて緋鶸に事の真相を確認しようと、緋鶸を抱き抱えると涙に濡れた顔を覗き込んだ。
「うん…かかさまがぼくを、たたいた」
「いつもか…?いつも弁慶は緋鶸に!?」
…それは虐待ではないか。
あの儚気で控え目な笑みを浮かべる弁慶が、そんな事をするなど信じられない。
何より、弁慶は緋鶸を大切にしてくれていたのだ。
「ううん。かかさま、いつもはやさしい…でも、たまにこわいんだ」
「どんな時に、弁慶は怖いのか教えてくれるかい?」
「わからない。けど、いっぱいたたいて、おこる……いなければよかったのにって」
緋色の瞳から零れる涙を幾重にも重ねた着物の袖で拭うと、緋鶸は舌足らずに言葉を続ける。
弁慶が初めて手を上げてたのは、二月程前だと云う。
「でも、いつもはやさしいよ。こわいあとも、ごめんなさいって…なでてくれる」
緋鶸は真っ赤に泣き腫らした顔に満面の笑みを浮かべて笑った。
「緋鶸……分かった、ありがとう」
「ててさま…くるっ、しぃ…」
ヒノエは一度、緋鶸は苦しいと身じろぎする程強く抱き締めてから、子を己の私室に戻るように促す。
次いで、その足で弁慶に当てている曹司へと向かった。
憤りを露にした慌ただしい足取りで戸を開くと、そこに弁慶は居たが俯いており表情までは分からない。
「弁慶っ!あんた…緋鶸に何をしたんだ!?」
「叩き、ました…緋鶸が…ヒノエと同じ目で僕を見ていたから……自分を抑えられ、なかったんです…っ」
開口一番にヒノエが叫ぶと弁慶は弾かれたように、脅えに染まる顔をこちらに向ける。
平然と開き直っているのなら責める事もできようが、弁慶は後悔に顔を歪めており、これでは叱咤する事もできない。
「…弁慶、何でそんな事したんだ?同じ目って何だ!?」
ヒノエは複雑な表情を浮かべると、自分がいない間に何があったのかを問い正した。
「緋鶸はヒノエに似てるんです…面立ちだけでなく仕草も…」
「はぁ?…それだけが原因なら、此処に来てすぐにそうなったんじゃない?」
自分が知る限り、ここ幾年か些細ないさかいはありはしたが、大事は何もなかった。
「先日までは、ずっとヒノエは傍にいて睦言をくれたでしょう?…不安になんて、なる必要がなかったんです」
九郎がいなくても僕には大切な家族がいると思えたから、ヒノエを信じ、あの子を愛す事ができた…弁慶はそう言葉を付け足す。
「…とにかく、まだ事情が把握できない……詳しく教えて貰おうか?」
「はい…。突然、ヒノエからの音沙汰が唐突に何もなくなって…不安で堪らなくなったんです」
気持ちが浮付き落ち着いてくれずそれが更に苛立ちを呼び、感情を隠す事ができなかった。
それに聡く気が付いたようで、幼子にしては口数の少ない緋鶸は真っ直ぐに弁慶を見つめていた。
「無垢なその緋色の瞳が僕を責めているよう思えて…っどうして、“ヒノエ”に非難の目で見られなければならないんだって…!」
「九郎の傍に居れなくなったのも、緋鶸を身籠ったのも、オレの所為だからね… 」
「…っごめん、なさい」
珍しく狼狽した弁慶の話は震える唇から小さな音となる。
「じゃあ尚更…緋鶸が憎らしく見えただろうね」
子の面立ちがヒノエに似ているのも災いして、その緋色がヒノエのそれと重なって見えた事だろう。
きっと、あの時の怨嗟が蘇ったのだ。
「嗚呼、あの子がいなければ…ヒノエがいなければ、九郎の傍に居れたのにって …穢れて醜い僕が言うんですっ!」
「次の瞬間には……叩いてた?」
「……一度では、おさまらなくて…っ僕は、!」
だが、すぐに自分に過ちに気付く。
罪悪感に押し潰されそうになって、緋鶸を抱き締めて幾度も謝罪の言葉を紡ぐしかできなかった。
「二人がいなければいいなんて、そんなわけはないのに!分かっているのに…っどうしても駄目なんです…!」
子がヒノエと重なる度に、後悔と怨嗟を繰り返してしまう…。
「いやなのに…嫌なのに!…止められないんです。先刻も、叩いて…」
叩いたその感触が色濃く残る己の手の平を覗いて、琥珀の瞳をきつく閉じた。
「いなければよかったのに、か…」
「ごめんなさい…そんな暴言、吐くつもりなんてなかった、!…可愛い僕の子に …僕とヒノエの子なのに!」
だが、目を閉じても脳裏に焼き付いた衝撃を受けた緋鶸の顔は離れてはくれない。
「愛してるのはヒノエです、嘘じゃない……でも、九郎が好きなんで…忘れる事なんて、できない」
「弁慶、オレはあんたを疑ってなんかない。…九郎を忘れろとも云ってないじゃん!」
弁慶が九郎にどれだけ固執し、彼の隣でどれだけ幸せそうに笑い、活きていのかを知らないわけではない。
青褪めた顔で、いつからか身に付けるようになった女物の着物を握り締めるその手を取ると、ヒノエは落ち着くようにと微笑んだ。
「ごめんなさい…でも、僕は…どうしたらよかったのか、分からないんです」
弁慶は感情を乱す事に疲れて、ヒノエに身を預け胸に顔を埋める。
微かにヒノエの愛用している香が薫り落ち着きを取り戻した弁慶は喚く事はなく、曹司内には赤く燃える火鉢が立てる音が響いていた。
「…ねぇ、僕の何がいけなかったの?…九郎の傍に居たいって願った事?緋鶸を産みたいって思った事?ヒノエを愛した事?」
何がいけなかった?総てがいけなかった?
「ヒノエ、教えて!答えて!僕が生きているのがいけないの?……僕は何処に居ても何をしても、厄災を広める鬼でしかないの?」
「…弁慶、違う…違う!あんたは鬼なんかじゃない!」
今弁慶が紡いだのは、幼心に刻まれ嫌でも覚えた周囲の蔑む嘲りの言葉なのだろう。
「オレはあんたが生きていて…産まれてきてくれて、あんたに出会えて…嬉しいんだ」
「ヒノエ……」
愛しい人の優しい声色が心地いい。
「緋鶸も分かってるさ。確かにアイツは泣いてたよ…でも、あんたを好きだと言ったんだ。あんたを愛してる…オレも緋鶸も」
「………うん」
恐る恐ると素直に弁慶は頭を垂れる。
「ゆっくりでいいって言っただろ……オレは嘘は吐かない、それが本気で惚れた相手なら尚更ね」
「ヒノエ…ありがとう。やはり、僕は君が好きです…」
「オレもあんたを愛してるよ」
自分が咎められるのは当然だ、幾らでも後で報いを受けよう。
でも、今は貰えた欲しかった言の葉に酔っていたかった。
しかし、久方振りの甘い刻ゆっくりと楽しむ暇などないようで、その時、頭を深々と下げた女房が無礼を承知で曹司に訪れる。
「ヒノエ様、弁慶様!緋鶸様のお姿が邸内に見当たらないのですっ」
恐る恐ると告げると、不手際を詫びた。
「緋鶸が!?」
「…っ何処へ行ったのか分かりますか?」
「おそらくは…お邸の外へ…っ」
薬湯を緋鶸の元へ運べばすでに姿はなく、慌てて確認すれば草履が無くなっていたと云う。
「分かった、お前は緋鶸の曹司に褥と火鉢の準備を頼む!」
火鉢はすでに置いてはあるが増やしておくに越した事はない。この雪の中出歩いたのでは身体が冷えてしまう。
「弁慶、行くぜ!…緋鶸の足じゃそう遠くにはいけないはずだ」
「…っええ、早く見つけてやらないと!」
女房へ応えもそこそこに、ヒノエと弁慶は競うように渡殿を駆けていく。
一瞬弁慶には気後れと迷いがあったが、緋鶸を心配する気持ちに偽りなどなく、それが足を動かしていた。
 : 0
: 0


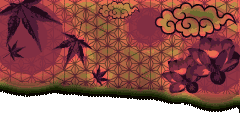

 : 0
: 0
