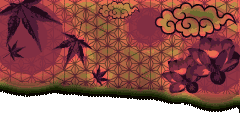

諷邪
季節は冬…―
紅葉を終えた木々は見目も寒々しく変わり、外気は冷える為に吐く息は白く滲む。
冬はそのように冷え込むのは当然なのだが、生憎と今過ごしている土地は奥州は平泉。
京や熊野とは気候の厳しさが違うのだ。
身を切るような寒さと、音もなく深々と降り積もる雪は、本当に油断ならない。
平泉は幼い頃を過ごした地である為に、弁慶はそれを身に凍みて知っていた。
「全く……そんな事は、わざわざ口に出す方が失礼かと思ったんですがね」
藤原秀衡から借り受けている高館の客間にて、弁慶は敷かれた褥に寝込む人物の熱い額に手を添える。
…熱は昨夜から、少しも下がっていないようだ。
先程から弁慶は、傍らに置いた赤く燃える隅の入った火鉢を時折調整したり、上衣を掛けてやったりと、甲斐甲斐しく世話を焼いていた。
今も水を張った桶に浸けて濡らした小さな布を絞り、熱い額にそっと乗せた処である。
「はぁ……まだ、手を離せない幼子でしたか…」
弁慶は大袈裟に溜め息を吐いてから、汗ばむ額に張り付いた癖のある緋色の髪を払う。
褥に力なく横たわるヒノエは、普段ならば文句の一つは必ず返してくるのだが、今ばかりは大人しい。
先程、飲ませた薬が効いており、深い眠りに落ちているのだろう。
ヒノエの様子がおかしいと気付いたのは、不覚にも昨日だった。
一人遅れて合流したヒノエが平泉に来てから数日、彼らしくもなく部屋に籠りがちだったのを妙には思ってはいたのだが…。
結局、実際に真意を確かめようとヒノエの元へ行ったのは昨日で、訪れれば彼は大きく咳き込んでいて…。
拒むヒノエを制して、慌てて病状を診れば、深刻な風邪。
風邪に耐えられなくなったのが昨日だとすると、患ったのはそれ以前という事になる。
恐らく熊野に居た頃からか…平泉へ下るその途中から体調は良くなかったのだろう…。
幼い頃に僅かな期間とは言え、ヒノエ自身も平泉で過ごした経験があるのだから、この地の厳しさを知っているはずなのだが…。
「しかし…何故、もっと早くに言わないのでしょうね…」
ヒノエなりの意地なのか、自らの体調管理ができなかった事への気恥ずかしさからなのか。
否、今はいつ源氏が攻めてくるかも分からない切迫した状況だからこそ、些細な事で迷惑を掛けたくなかったのか?
何にせよ、自分や神子には知られたくはなかったのだろう。
弁慶はそのヒノエの意を汲み取り、皆には軽い疲労だと伝えたが、その嘘が持つのも精々、二日である。
それまでに治ってくれれば良いのだが、この分ではそれは見込めそうにない…。
「どうしたものでしょうか…」
「…………弁慶、煩い」
一人呟いた言葉に返ってきたのは、いつもの澄んだ声色ではなく枯れたヒノエの声だった。
「おや、起きていたんですか…ヒノエ?」
「……すぐ横にあんたがいるんだ、目くらい覚めるよ…」
実際には、何処か不安の色を含んだ弁慶の声に起こされたわけではないのだが、ヒノエは煩わしそうに言ってみせる。
次いで、鈍く痛む重い頭に手を当て、大きく熱い溜め息を吐いた。
「調子はどうですか?」
「最悪」
「……でしょうね」
問われても返答するどころか、痛む喉から声を出すのも億劫で、短い言葉を小さく返す。
「全く…こんなに大きくなったのに、肌を晒しているからですよ。愚か者」
「…煩い」
「こんなにも労わっているのに、その態度ですか…躾がなっていませんね」
「何処がだよ…」
半ば据わったような瞳でヒノエを貶めるような言葉に、ヒノエは反論も出来ずに小さく悪態を吐いた。
「何か食べますか?」
「食べれると思ってんのかよ…」
ヒノエの言い分はもっともなのだが、彼は昨日から何も口にしてはいない。
僅かでも身体に入れなくては、身体の回復力にも薬の効きにも影響する。
「でも、食べなくては良くなりませんよ」
「……吐く」
それでは本末転倒だ。
弁慶は苦笑すると、顎にしなやかな指を当てて思案してみせる。
「では…食べ易い粥か何かを作ってきましょうか?」
「……あんたが?」
「ええ」
提案した途端に嫌悪を隠そうともせずに頬を引き攣らせたヒノエに、弁慶は顔色を変えずに肯定した。
確かに自分は不器用な方であるが、人並みには作れるように努力をしたのだから、食べれるくらいの料理は作れる。
「それこそ、吐くだろ」
「おやおや…そうなり掛けた時には、接吻で塞いであけますよ」
あまりの悪態の吐きように弁慶は悪戯を含んだ声色で、ヒノエの唇をなぞってみせた。
「はっ、冗談…」
それに対してもヒノエが鼻で笑った後に緩く首を振る様子に、弁慶は哀し気に眉を寄せると、彼の顔を覗き込む。
「ヒノエ、薬を飲むにも、食事を取らないといけない事くらい分かるでしょう」
熊野の頭領としての役目を果たしながら、九郎や自分を庇う為に奮闘した彼の疲労は相当なものだろう。
そうでなければ、幼い頃から病になど殆どかかった事のないヒノエが、倒れるわけがない。
そんな状態であるにも関わらず、自分の元へ…嫌、これは自意識過剰だろう、… 皆の元へ駆け付けてくれたヒノエを労いたいのだ。
「…ヒノエ、お願いですから。僕の言う事を聞き入れて下さい」
「分かったよ…」
言の葉に込めた想いが伝わったのか、ヒノエはようやく頷いてくれた。
それに弁慶は嬉し気に微笑むと、軽やかな動作で立ち上がる。
「果物も食べますか?…ヒノエが望むのなら、九郎から柿を一つ頂いてきますよ」
「あんたが九郎の処に行くくらいなら要らないね」
まだ力の入らない手でヒノエは弁慶の身に付けた着物の裾を掴むと、軽く力で引いてみせた。
「ふふ、一人になるのが心細いんですか?」
「別に…」
「……大丈夫ですよ、ヒノエ」
気恥ずかしいのか僅かに目線を反らしたヒノエに、弁慶は膝を折り顔を近付ける。
「丁度、夕餉の時刻です。厨の準備もできているでしょうから、すぐに戻れますよ…」
次いで、八葉の証である紅が彩る額に、唇を落とし音を立て軽い口付けを贈った。
「ヒノエ、できましたよ。起きていてくれましたか?」
先程の言葉の通りに、一刻も経たずに弁慶は戻ってきた。
「あぁ、起きてたよ。随分、早かったなんだな…」
「…ふふ、君にそう言いましたから」
湯気を立てる粥が盛られた器を乗せた盆を自身の傍らに置き、弁慶は優し気に微笑む。
「…ん」
ヒノエは随分と酷い倦怠感に支配された身体を無理に動かし、上半身だけを褥から起こした。
「熱はどうですか?」
「あんたなら、診て分かるだろ」
「…良くありませんか。まぁ、食事を取れば、身体も温まるでしょう」
額を冷やしていた布を落ちる前に押さえ弁慶に手渡すと、彼は熱を持ったそれを慣れた手付きで桶に浸す。
「ほら、食べさせてあげますよ」
「はぁ?餓鬼じゃねぇんだから…」
「いいじゃないですか、幼子の頃は君が風邪を患う事なんてありませんでしたからね」
弁慶が粥を掬った匙をヒノエの口元へと運ぶと、彼は眉を僅かに寄せる。
「…今くらいは甘やかせて下さい」
「餓鬼の頃、できなかったからって……」
流石に人目がないとは言え、この歳になって人に食べさせてもらうという行為には、羞恥が付き纏った。
「………ぃやだ、いらな」
「はい、召し上がれ」
だが、弁慶は文句の言葉を紡ごうと、僅かに開いたヒノエの口に匙を押し込んだ。
「!!?…ぁつ、!!」
とろみのある熱い粥が舌に落ち、口に広がった途端にヒノエは口を押さえた。
「熱っ…!」
粥の味を味わう間などあるわけもなく、を舌を出し火傷を負ったそれを外気で冷やそうとする。
「この、弁け…っあんた…何、!」
「嗚呼、すみません。すぐに水で冷やしましょうね」
水の注がれた杯を仰ぐとヒノエの頬を両手包み込み、含んだ冷えた水をヒノエの口に移す。
「っおい、…っん、!?」
「…ふっ…ん、っんん…、!」
どちらともなく舌を絡めて口付けを深めていくと、火傷をした部位が僅かに痛んだ。
「っ…!」
互いに接吻を存分に堪能してから、名残惜し気に唇を離す。
淫らに水音を響かせていた分、口に移された水は、顎を伝い零れ落ちていた。
「おやおや…もう一度、飲ませないといけませんね。…今度はきちんと飲み込んで下さいよ」
心地よく冷えていた水は二人の熱い体温で温くなっている。
弁慶は顎を伝う液体を拭うと、口の端に笑みを浮かべてみせた。
「ねぇ…薬師が患者に手を出していいわけ?」
「おや、これは治療ですよ?…僕は優しいですから、小さな火傷にも匙を投げたりしないんです」
お互いに何処か含んだような笑みを浮かべて、手を合わせ指を絡め合う。
どちらかが言葉を紡げば唇が触れそうな程に、顔が近い。
「風邪が移るよ、弁慶?」
今は不測の事態にも対応できるように体調は万全に整えておくべきなのだ。
こんな時期に、みっともなく風邪を患うのは自分一人で十分である。
「昨夜からずっと…君と同じ部屋にいるんです、今更ですよ」
それに、…と前置きしてから、弁慶は言葉を続けた。
「先程、ヒノエが甘えてくれたのが嬉しかったので…そのお礼に、今度は僕が甘えてあげますよ」
相も変わらずに尊大な物言いだったが、言った弁慶の頬が僅かに薄紅に染まっていたのは見逃さない。
「へぇ…ただ、あんたが寂しいだけだろ?…オレに構ってもらえなくて、さ」
「…っ、?」
自分の赤みを差した頬に触れた目聡いヒノエに、弁慶は更に頬を染め上げた。
それを誤魔化すように、わざとらしく、小さな咳払いを一つ。
「……とりあえず、粥は冷めない内に食べてしまいましょうか」
今度は息を吹き掛け、きちんと冷ましてから、ヒノエの口の中へ匙を押し込んだ。
「味はどうですか?」
「……美味しい」
口に広がった粥の味に、ヒノエは心底意外そうに緋色の瞳を丸くする。
以前に半場強制的に食べさせられた弁慶の薬膳料理なるものは、食べられた物ではなかったが、これは違った。
「粥くらいなら、僕でも作れるんですよ?」
二人きりの時に他人の名を出されるのを嫌うヒノエに合わせ、譲のようにはいかないが…そう始めに付け加えるはずだった言葉は呑み込んだ。
「いつもこうなら、イイんだけど…ね」
弁慶が口元まで運んだ二口目の粥に、ようやくヒノエは自ら口の中へ招き入れた。
「ヒノエ、今宵もずっと看病してあげますからね…」
三口目のそれを掬った弁慶は、実に優し気に微笑んだ。
「…て、あんたが先に寝てどうすんだよ」
大分痛みの収まった頭をヒノエは呆れたように押さえると、先程まで微睡んでいた弁慶に目線を送る。
自分に掛けられていた上衣を一つ、身体が冷えぬようにと、弁慶の身体に乗せて覆った。
「まぁ、昨夜から気を張ってたんだろうけど…」
弁慶は殆ど付きっきりで、自分の看病を続けてくれていたのだ。
口では可愛くない事ばかりを吐くが、心配はしてくれていたようで、心労は僅かなりともあったのだろう。
心地よく聞こえてくる規則正しい寝息に、ヒノエは蜂蜜色の緩やかな髪を弄ぶ。
「……ん、…ノエ」
「ぁ、起こしたか、?」
煩わしいのか、弁慶が褥の横で僅かに身動きしたのに、慌てて蜂蜜色を指に絡める遊戯を止めた。
起こしたわけではないようで、琥珀の瞳は瞼に隠れたままだ。
ほっ…と、胸を撫で下ろしたヒノエの耳に、極…小さくだがはっきりと紡がれた弁慶の寝言が落ちる。
「ヒ、ノ…ェ………好き…」
途端に、ヒノエの身体の動きが表情から指先に至るまで綺麗に止まった。
「馬、鹿…それ、反則だろ……っ!?」
滅多に言っては貰えないそれの不意打ちに、ヒノエは風邪の所為ではなく顔を赤くした。
その傍らで、火鉢の炭が燃えて軽い音を立てていた…。
終り。
 : 0
: 0


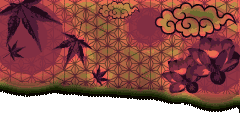

 : 0
: 0
