|
|
ログイン |
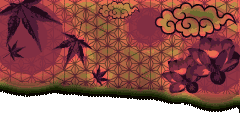

「…!」
自分が誰かと言い争う夢を見た…ような気がするのだが、よくは覚えていない。
分かっているのは伏せた身体全体に振動が伝わってくるという事。
「ん…ん…、」
徐々に、暗闇に落ちていた意識がゆっくりと覚醒していくのが分かる。
狭い塗籠のような場所にいるのは分かったが、邸の中ではない。
何故なら、揺れているからだ。
荷を運ぶ車の中か何かなのだろうか…?
少しばかり高く積まれた荷を覆う為の薄汚れた布は、乱雑に掛けられていたらしく布の隙間から、傾いたまぶゆい陽の光が差し込んだ。
刻は、まだ夕暮れ前のようだ。
起き上がろうとして身体に痛みが走った。
「…痛、っ」
特に頭の鈍い痛みが強い。
後頭部に触れてみると瘤のようなものができ、腫れていた。
恐らく殴られたのだろう…と思ったが、違うようだ。
先程まで、自分は鬱伏せに気を失っていた。
その状態にだった時、頭部があったであろう辺りに、角の鋭い木箱が幾つも不自然に転がっている。
積み重ねられた荷が何かの拍子に崩れ、頭を襲ったのだろう…。
しかし、怪我の理由は推測できても、憶測のしようがない事がある。
例えば、ここは何処なのか?何をしていたのか?
そして、“自分が誰なのか?”
…そう、幾ら考えても、自分の名さえ分からなかった。
これは、いわゆる“記憶喪失”と云うものなのだろうか?
「困ったな……」
何か思い出せないかと、思案する内に手が自然と髪へと伸びる…が、何も掴む事ができない。
どうやら、考え込む時に髪をもてあそぶ仕草が自分は癖だったようだ。
そして、記憶があった頃の自分は髪を長く伸ばしていたらしい。
もっとも、今の自分の髪は肩の辺りで切られており、毛先も相当に乱雑だったのだが…。
どうしても髪に触れないと身体を落ち着かないようなので、髪に指を通した。
すると、指に絡み付いてきたのは金とも茶とも違う、その間のような…蜂蜜色だった。
「……え…っ!?」
とにかく驚いた。
記憶が無いと言ってもある程度の常識ならば覚えている。
この色は鬼と呼ばれる妖の色…、という事は、自分は鬼なのか?
…いや、もし自分が鬼ならば、自身の毛色が鬼の色をしていたからと言って、驚くわけはないだろう。
ならば、自分は人間のはずだが、……まずい事に変わりはない。
他の者に見られてしまっては、自分が鬼扱いされるのは間違いないのだから…。
頭を隠す布は物はないかと自分の姿を改めて見ると、黒い外套を身に付けているのが分かった。
「やりますね…」
思わず、過去の自分を誉め讃えてしまう。
しかし、荷と共に運ばれているという事は、自分は荷と同等の扱いなのか、自らここに忍び込んだのかのどちらかだろう。
どちらだとしても、自分の置かれた状況も事情も理解していない自分は、荷の主に会うのは御免被りたい。
ならば…と、気付かれぬようにそっと荷から飛び降りた。
速度の遅い荷車は高さも然程ない、着地の衝撃は大した事なかった。
「…っ…、と…!」
軽やかに地に膝を付き顔を上げると、唐突に荷から現れた人影に路行く人々の好奇の目線が注がれる。
「こほん…っ」
わざとらしく、咳払いを一つ。
騒ぎになり荷の主に気付かれる前にと、さも平静を装い立ち上がった。
降りた地は大きな栄えた都だった。
中でも高く大きな邸が並ぶ一郭の一際、立立派な邸に瞳を奪われた。
ただ雅な外観に惹かれたわけではなく、気になったのは懐かしい思いと共に視概観を覚えたからだ。
…何処かで見た事があるような気がしたが、やはり思い出せない。
まぁ、自分がこの都で育ったのならば、視概観があったとしても何の不思議でもないのだが…。
「あの…こちらのご立派なお邸は?」
門にいた雑兵に問いを掛ければ、返答はすぐに得られた。
「藤原秀衡様の御邸、伽羅御所だ」
藤原秀衡、それが奥州平泉を治める者の名だという事はさすがに知っていた。
「…では、此処は…平泉?」
「何を言っている?」
つい一人納得し頷いてしまったが、聞こえた雑兵の不審そうな声に慌てて言葉を返す。
「嗚呼、すみません。最近、こちらに越して来たばかりなもので…」
「熊野が源氏の手に落ちてから、移住民は多いからな。お前もその類か?」
口から出任せの言い訳だったが、幸いにも相手は納得してくれたようだ。
「…ええ、そうなんです」
「秀衡様の元に来たからには安心だぞ」
雑兵の言葉に適当に相槌を打ちながらも、心は何処か上の空だった。
熊野と聞いた途端に、一瞬だけ鼓動が早く脈打ったのだ。
記憶のない状態が気持ちが悪い。
何故、こんなに一つ一つの事に動揺しなければ、ならないのか…。
二、三言言葉を交した後に、親切な雑兵と別れを告げ、宛てもなく歩き出す。
「平泉は平和なようですね…」
さりげなく周囲を伺っているが人々の顔は皆、穏やかで活気に溢れている。
「…さて、」
これからどうするにしても、やはり名がないのは不便だ。
本来の名は今は思い出せそうにないし、どうせ幾つもの名を持つ者も少なくない。
ならば、名乗る名くらい自分で決めてもいいだろう。
「……何としたものかな…」
ふと、見た西の空は夕暮れで、大きな陽と夜の帳が降りかけて…緋色と藍が混じり合い何とも不思議な色で空を飾っていた。
いつかに誰かと、こんな夕陽を眺めたような気がして…酷く懐かしい想いにかられる。
その時、自分の隣に居たのは…誰だったのだろう。
「そう…だな、……夕夜…と、でも名乗ろうかな…」
夕焼けと夜の舞舞台は見ていてとても美しかったから…。
夕夜と名乗る事に決めた。
それからの日々は大変だった。
今は誰も使っていない古い庵を自分の家として、様々な仕事を経験した。
…中には、少しばかり怪し気な仕事もあった。
そんな中で、自分が薬師としての知識と技術を持っている事を知った。
それからは、薬師として過ごしていく…。
自分の薬師としての腕はいいらしく、そこそこに愛されている。
消えた記憶が戻る事は相変わらずないが、“夕夜”としてそれなりに平和に暮らしていた。
自分を大きく揺れ動かす懐かしい想いに駆り立てる緋色の彼に出会ったのは、季節が四回程巡った頃だった…。
つまらない…―
ヒノエは少々癖のある柔らかな緋色の毛先を指に絡めると、何度目になるか分からない溜め息を吐いた。
平泉で暮らし始めたヒノエは表面上は、今までと同じ様子を繕っている。
…だが、以前のように心が踊る出来事も、心を熱くさせてくれる事も、…何もない。
刻が過ぎるのを待つように、ただ生きているだけ…。
そんな風に過ごしていたある日、一人の女に出会った。
儚げに微笑む優しい表情と大胆な程、妖艶な様に惹かれて、一夜だけ床を共にした。
お互いに、その夜だけの付き合いのつもりで…。
そんな風に遊ぶ事はよくあったのだから、お互いに二度と会う事はない事も知っている。
たが、一年程の月日が過ぎた頃、再会の日は唐突にやってきた。
自分の邸に現れたのは、怯えた様子のあの日の女と、憤りを露にしている一人の男。
話を聞くと二人は夫婦で、あの当時からの婚約者だったとか…。
つまり、女はあの時点で結婚を間近に控えていたらしい。
結婚に不安を感じたのか、自由に遊べなくなるのが不満だったのか…自分を誘ったのは女の方だった。
断じて、自ら誘ったわけではない。
その時の自分は、そもそも女が結婚を控えている事どころか、恋人がいる事さえ知らなかった。
しかし、一夜の間違いが祟ったのか女は孕んだようだ。
当然、夫は激怒したが女を溺愛していたようで、…自分なら結婚を控えた身で男を誘うような女は御免だが、怒りの矛先は自分に向いた。
名を聞いただけ…しかも、自分が告げたのは“ヒノエ”だったのに、邸を見付け出して来るとは見上げた執念である。
説明もそこそこに自分を殴り付けた後に、女が産んだ赤子を自分へ押し付けてきた。
一夜とは言え床を共にしたのだから、心当たりがないわけではないが、本当に自分の子供かどうか一瞬、疑ってしまった。
だが、赤子を見た途端に自分の子供だと確信する。
産まれた赤子は、蜂蜜色の髪に琥珀の瞳…オレの血を色濃く継いだらしく稀な藤原の血を引いているようだ。
以前に彼だけが母親からこの色合いを受け継いだのだ、と聞いた覚えがある。
…自分の子がこの色で産まれる確率は皆無ではないのだ。
夫からすれば憎むべき男…自分の子供を生かして連れて来てくれるとは…。
そう感心し感謝までしかけたが、次に続いた言葉にその気持ちはすぐに消えた。
「その赤子は呪われてた鬼子だ!殺すと私達にも災いが起きるだろう…」
鬼子…この色合いの者をそう呼ぶのは、彼を鬼と呼ぶのと同じ事だ。
瞬間、頭に血が登り掛けたが、何とか怒りを抑え付ける。
男は言いたいだけ自分を罵る中、時折、女はおずおずと口を挟みたそうにするが、結局はすまなそうに目を伏せるだけ。
…夫に対しても自分に対しても引け目と負い目を感じて、強く出れないようだ。
しかし、男の罵り方は幼稚なもので腹は立たかなったし、怒鳴る度に裏返る声が耳障りだった程度しか記憶に残っていない。
しばらくすれば、足音も荒く去って行き、女は慌てたようにその後を追う。
自分の腕に抱えた暖かい温もりを残して…。
「………」
「ふ……ぇっ」
呆然とし掛けたていた自分を現実に戻すように、赤子がしゃくり上げた。
「え!?」
「ふぎゃぁあ」
途端に泣き出すややをどうにかしようとするが、赤子を育てた事などあるわけもなく…。
「コイツは…、少し弱ったね…」
「っああぁ…ふぎゃ…っふ、ぇ…あぅ……」
いつぞやに見たように腕に抱えたままあやすと、徐々に泣き声が小さくなっていく。
何とか泣くのを止めてくれた赤子に、ほっと胸を撫で下ろした。
だが、自分には呆然としている時間はないようである。
実際問題として、流石に一人で赤子を育てる自信はない。
…とりあえず、泰衡辺りにでも相談しようと、その足で伽羅御所へ向かった。
政の執務が詰まっていたらしい泰衡は、突然の訪問者に常よりも不機嫌そうに眉間の皺を刻んだ。
後に、来訪者の腕に抱えられた赤子を見、その瞳を僅かに見開く。
「何だ……その赤子は?」
「オレの子に決まってるじゃんか」
口の端に笑みを浮かべてから答えると、泰衡は心底、怪訝そうな顔をした。
至った経緯を説明すれば、思い切り眉を寄せながらも泰衡は、赤子を育てる上で必要な物を整える手筈を整えてくれた。
この日から、それまで日々送っていた廃退的な暮らしとは無縁になった。
彼のいない日々にも生き甲斐を見つける事ができた。
この赤子に自分は救われた…感謝をしなくてはならないだろう。
赤子の名は、姿が似ている彼の幼名から一文字もらい、若―わこ―と名付ける事にした。
名前にあやかったお陰か、育っていく内に、どんどん彼に似ていくのが目に見えて分かる。
歳の頃が四つ程になった若は、本当に顔立ちがそっくりだ。
一日追う度に、若が成長し育っていく姿を見るのが、赤子の時に増して楽しみになっていく。
ヒノエが何気なしに泰衡にそう話すと、彼は意外な言葉を呟いた。
「若はとても、アイツに似てるんだ。きっと、聡い子になる…」
「…光の君、か」
恋大き者に例えられて、ヒノエは大袈裟に肩をすくめてみせる。
「昔ならともかく、今は誰彼にと声を掛けちゃいないぜ」
「ふっ、無自覚、だな…」
そう反論すれば、鼻で笑われた。
「さながら、子は紫上と云ったところか…」
「…おい、泰衡ぁ?」
泰衡はそう言葉を残し、執務に戻っていった。
忙しい身であるにも関わらず、何だかんだとこうして、自分と話す時間を作ってくれる。
それは嬉しいのだが…、今の言葉は?
「光の君に…紫の上、?」
どういう意味かと思案したが、答えを出すのに大分掛ってしまった。
しかし、泰衡の言わんとする事を理解すれば、ある意味では適切な表現だった。
藤壷の影を追い続けた光の君に例えられたという事は…。
若は彼ではないのだから、同一視するな…と忠告してくれたのだろう。
「……言ってくれるじゃんか」
少しばかり癖のある緋色の髪を巻き込み、軽く頭を掻いた。
若には、教養の一貫という名目で、兵法や薬の製法などを無意識に教えていたのだ。
……確かに、そういう傾向があったのは認めよう。
「若…ごめんな」
すぐ隣の褥で安らかに寝息を立てる幼子の頭を、眠りを妨げない程度にそっと撫でた。
それ以来、ある程度に必要な教養などを覗いて、できる限りには自由にさせている。
「若、嫌なら無理に続けなくてもいいんだぞ?」
「ううん。若は父様から、おしえてもらうの、とてもすきです」
書物を広げる若に問い掛けても、いつも少し舌足らずにそんな事を言うので、勉学に関しては実際にはあまり変わらなかった。
変わった事と言えば、若が一人で外へ出歩くようになった事だ。
以前から若が外で遊ぶのを好きな事は知っていたが、彼に似た髪色で差別されないか不安で、一人で出す事はなかった。
だが、いつまでも閉じ込めてはおけないと思い直し、今では一人で出歩いても咎めない事にしている。
「…いってきますね、父様!」
「嗚呼、分かった。…ちゃんと、気を付けるんだぞ?」
きちんと身支度を整えさせ、挨拶をさせてから戸口まで見送った。
自由に出歩けるのが、相当に嬉しかったのか、若は一旦外へ出ると、なかなか戻って来ない。
「遅いな……」
…しかし、今日は特別に遅かった。
仕事を終え邸に戻ってきても、若はまだ家に帰って来ていない。
外はとうに夕暮れを過ぎている。
夜の帳が降り掛け、暗くなり初めている程だ。
常に告げずとも日が暮れる頃に戻ってくる若にしては、遅過ぎる…。
不安が過ぎり、探しに行こうと戸へ向かった時に丁度、探し人…若が飛び込んできた。
「父様ぁー、父様!」
「…っ若、遅いだろう!心配したんだぞ!」
若の小さな身体を抱き抱えると夜風に吹かれた為か、少しばかり冷えている。
「ほら、もっと奥まで行くぞ。身体がこんなに冷えて…っ!暗くなる前に帰って来ないと駄目だろう!」
箪笥から少しばかり厚目の衣を引っ張り出り、肩の上から掛けてやった。
「ほら、言う事があるだろう?ちゃんと教えたはずだ」
「はい!…ごめんなさい、父様。でもでもね、父様ぁ!」
「こら、若っ!」
厳しい口調で咎めるが、当の若は何故か楽しそうにはしゃいでいる。
「きいて、父様!若は、若にそっくりなかおをしたひとに、あいましたっ」
「だから………え?」
更に紡ごうとした咎めの言葉は、口から落ちる事はなく呑み込まれた。
ヒノエの些細な変化には気づかずに、若は先程の出来事を伝える為、言葉を紡ぐ。
言う事を要約すれば、いつもより遠くへ出向こうと夢中になって遊んでいる内に、調子に乗ったようで右も左も分からなくなったのだと言う。
困り果てて泣く事にも疲れた時に、その若に似た人物が優しく手を引いてこの邸まで連れてきてくれたとの事だ。
「とても…とてもね、やさしいひとでした。…若を父様のところまで、つれてきてくれました」
若に似た顔立ち…嫌、これは正しくない。正確には、若が似ているのだ。
そして、若に似た人物は自分の知る限りは一人しかいない。
「まさか…っ?」
確信が得られたわけではないから…小さく呟く。
思い至ったあくまで可能性のそれに、心臓が大きく鼓動した。
「若っ、お前は此処でちょっと待ってるんだ!いいか、外に出たら駄目だ!」
「…わかりまし、た…?」
「よし、いい子だ」
ぎこちないながらも幼子が言い付けに頷いたのを見てから、ヒノエは慌てて外へ飛び出した。
まさか…まさか!?
若を邸まで送り届けた人物は、まだそんなに遠くへは行っていないはず。
幸いにも、この辺りの路は大きな路一つが主流になっており入り組んでいない為、人を探すのに然程苦労しない。
程なくして、ヒノエは人混みの中に目的の人物を見付けた。
灯りを持って来ていなかったが、探し人本人が手にした灯籠に照らされていた為、姿はよく見えた。
昔から見慣れていた彼の背に、とてもよく似た後ろ姿が…。
「あ、あのっ…!」
無意識の内に駆け寄り、後ろからその人物の腕を強く捕まえた。
「…あんた、あんたは…!」
「ぅわっ…!?」
何の前振れもなく、身体を掴まれたのに驚いたようで、こちらを振り返る。
……思わず、絶句した。
「ど、…どう、しました?」
驚きに琥珀の瞳を大きく見開くその顔は、自分の知っている彼と同じ…。
蜂蜜色の長かった髪は、肩の辺りで乱雑に切られていたが、美しさは損なっていない。
「弁、慶…」
口から勝手にその名が音と鳴って落ちた。
「ぇ……弁、慶?」
見知らぬ緋色髪の男に呼び止められただけでも不思議なのに、聞き覚えのない名で呼ばれた…。
夕夜は訝し気に眉を寄せたが、弁慶とは誰か…そう問い掛けようとした途端に、今度は痛みに眉を寄せた。
痛いっ…!
今まで経験した事のない頭の中から響くような痛みだった。
「弁慶、…っ弁慶だろ?」
緋色の髪の男は必死な形相で切な気にその名を繰り返す。
っ痛い…痛い!
その度に痛みに襲われ、頭が割れそうになる。
「弁慶、生きて…っ!」
「止めて!!」
堪らず、頭を抱えて悲鳴に違い声を上げた。
「弁慶、どうし…」
「っお願いし…す!その名を呼ばないで下さ……頭が…痛い…ん、です…っ!」
瞳が涙に揺れて目尻が濡れてしまった。
相手を見上げていた間、涙に潤んだ、さぞ情けない顔をしていただろう…。
「あっ、…ごめ、ん…!」
自分よりも背の高い緋色の男は叱咤された子供のように、悲し気に顔を伏せた。
「い…いえ、こちらこそ…すみません」
そんな顔をされたのでは、怒る気にもなれないし、そもそも、彼は自分を“弁慶 ”という誰かと人違いしただけだ。
自分が勝手に取り乱しただけで、彼は悪くなどない。
「…多分、疲れが溜っていただけでしょうから。気になさらないで下さい」
苦笑したように笑みを浮かべると、身に付けた黒い外套に手で触れる。
「…っ!」
その仕草、その表情…全てが記憶に鮮明な弁慶の姿と重なる。
ヒノエは、目の前にいる人物は間違いなく弁慶なのだと確信した。
何年もの間、ずっと弁慶が死んだと思い込んでいたが…。あの時と同じに、その場を見たてはいなった。
生きている可能性は低いが全くなかったわけではないのだ。
何より、…自分が弁慶を間違うはずはない。
「僕は薬師をしている夕夜といいます。君の探している方とは、きっと別人ですよ」
しかし、弁慶…嫌、夕夜と名乗った人物は、残酷な程に綺麗な笑顔でそう言い切った。
「夕、夜…」
「ええ。…君の名前は何と言うんですか?」
聞き慣れない名に戸惑いを隠せない…。
「オレ?オレは…ヒノエ、かな?」
「ヒノエ…ですか」
「まぁ、ね」
改めて名乗るのは、何処か気恥ずかしいものがある。
まさか、彼に名を問われる日がくると思わなかった…。
「随分、含んだ物言いをするんですね…君は…」
「名乗る名を自分で決めてるだけだよ」
それにしても、これが自分を知らない演技だとしてはおかしい。
「ふふ、それなら…僕と同じですね」
「は?夕夜…それは、どういう、?」
やはり何か事情があるのかと、ヒノエが問うの前に、夕夜に遮られてしまう。
「おや、その傷…」
まじまじと半端に伸ばした髪に隠した片目の傷に、夕夜の目線が注がれた。
「……大丈夫ですか?古い傷のようですが…」
洞察力が優れた彼の薬師らしい言葉、…演技だとしたら、こんなわざとらしい問いなど掛ける必要がない。
だとすれば、この傷を刻んだ事を……覚えていない?
「…ああ、これは…たまにうずくくらいで…痛っ」
言った傍からうずいた傷に、ヒノエは手で触れた。
夕夜はヒノエの手をそっと払い傷の痕に優しく触れた後に、小さく呟く。
「嗚呼、いけません。薬を調合した方がいいでしょうか…でも、今の刻では…… 」
「ぁ……、」
その常人よりも僅かに低い体温に、ヒノエは心地よい懐かしさを覚えた。
「そうだ。…よければ、明日、僕の庵へ来て下さい。薬を用意しておきますから」
「……わかった」
傷自体は完治していたし、先程も言ったように時折、うずくだけだったが、彼に会える口実ができるのは嬉しかった。
「では、ヒノエ…明日、待ってますね」
夕夜に優しく微笑まれると、心臓が高鳴り、一気に頬が蒸気したのが分かる。
ずっとずっと、忘れられずにいた愛しい人…。
本音をいうならば、一時でも離れるのは惜しい。
だが、彼は本当に何も覚えていない風だった。
そんな彼…夕夜に、いきなりに迫ったところで、何になるだろうか。
あの時のような事を繰り返さない為に…今度こそ、大事なものを見落とさないようにしなければならない。
焦る必要などないのだ。
彼が生きていた…今は、それだけで…。
ヒノエは、持て余しそうな様々な想いを、無理矢理に閉じ込めた。
 : 0
: 0
